2019年09月02日
NHKに、いじまも・井澤氏登場!
NHKニュースウェブより
「握手」でいじめ、なくなるの?
2019年8月26日 15時48分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190826/k10012048901000.html?utm_int=all_side_ranking-social_001
ある小学校で起きたいじめ。先生は両者を一緒に呼んで、「仲直りの会」というものを開いたそうです。いじめを受けた子どもは自分の意見を言えなかったのに、最後に先生が求めたのは、両者の『握手』でした。子どもはその後、学校に通えなくなりました。(社会部記者 勝又千重子)
二重に傷つく子どもたち
この対応、さすがにおかしいのでは?と思い、専門家にも意見を求めました。
聞いたのは、子どもたちのいじめ相談に乗っている「いじめから子供を守ろうネットワーク」の井澤一明代表です。
(井澤さん)「子どもたちに話し合いをさせる過程の中で、加害者からいじめた理由を被害者は聞かされる。すると悪口を言われるだけになってしまって、最後にいじめられた方も悪いから握手をしましょうとなる。これでは言いつけたなと言われて、いじめがひどくなることはあってもよくなることはない」

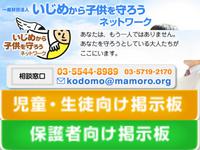
「いじめから子供を守ろうネットワーク」の井澤一明代表
http://mamoro.org/
児童・生徒向け掲示板
http://kodomo.mamoro.org/
保護者・大人向け掲示板
http://otona.mamoro.org/
2019年07月30日
NHKべきおばけ、実は本当に霊のしわざ!

NHKウェブより
とり憑かれてませんか? “べきおばけ”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190729/k10012012961000.html?utm_int=all_side_ranking-access_005
2019年7月29日
~~~~~~~~~~~~~~
大人の「引きこもり」について上・中・下
2005.09.06ザ・リバティ・ウェブより抜粋

2005年9月号 大人の「引きこもり」について(上)
https://the-liberty.com/article.php?item_id=271
2005年10月号 大人の「引きこもり」について(中)
https://the-liberty.com/article.php?item_id=277
2005年11月号 大人の「引きこもり」について(下)
https://the-liberty.com/article.php?item_id=286
病的に引きこもる人は何かで心が傷ついている
非常に病的な人であって、「絵画などの芸術に打ち込む」「何かを熱心に執筆している」「瞑想などの宗教修行に打ち込む」というようなことではなく、ただただ、「人と会うのが嫌。外へ出るのが嫌」という思いで、どこかに閉じこもっている人もいます。こういう人は、身内や友人が買って差し入れてくれる弁当などを食べて生活しています。
そのなかには、明らかに悪霊に憑依されている人もいます。
こういう人を社会に復帰させるには、どのようにすべきでしょうか。
こういう人は、基本的に、成長して大人になるまでのあいだに、何かで心が傷ついていて、その傷口がふさがっていないのです。そして、その傷口から膿が出てくるような状態なのです。
いま、BCG(結核予防のためのワクチン)の接種は非常に簡単になっていますが、昔は、それをされると皮膚に大きな跡ができ、夏になると、そこから膿がじくじくと出てきて痛かったりしたものです。
病的に引きこもる人には、ちょうど、そのような感じで、昔、心にできた傷口があり、外界と接触すると、何かのときに、その傷口が開いてしまうのです。それが嫌で、外部との接触を避けるわけです。
このたぐいの人を癒すには絶対的な愛が必要です。
それは、その人に対して、「絶対に悪く言わない。ネガティブ(否定的)なことを決して言わない。絶対に攻撃しない」ということです。そういう人には心を開きます。
しかし、「相手の行動によって、ほめたり怒ったりする。どちらになるか分からない」という人には、身構えてしまい、心を閉ざすのです。
すなわち、心が傷ついていて引きこもるタイプについては、「絶対善意の人が出てくれば心を開くだろう」ということが言えます。
このタイプに対しては、「相手の性格なり言動なりが、現象的には、どれほど悪く見えても、『これは自分自身が既成観念でかなりやられているのだ』と思い、相手のなかから、神の子、仏の子の部分を拝み出して、相手を絶対に責めない、悪く言わない、将来を悲観しない」ということが大切です。
「この世に生まれてきただけでも、いいではないか。命があるだけでも、いいではないか。何か意味があって、こうなっているのだろう」と思い、相手を排斥しないで受け入れる人が出てくると、その人に対しては心を開くようになるのです。
そういう人が傷ついたきっかけは必ずあります。子供時代に、「親の言葉で傷ついた」「学校で友達に傷つけられた」「塾で先生に傷つけられた」など、何らかの原因があるのです。
異性によって傷つけられる場合もあります。男性なら女性に、女性なら男性に、たいへん傷つけられたわけです。
ただ、それはよくあることで、多くの人が体験することです。それを乗り越えていかなくてはなりません。船が航海に出れば傷むように、人生を無傷で生ききることはできないのです。
男性が女性をデートに誘うと必ず受け入れられるのであれば、大変な世の中になります。誘った女性は、みな、ついてきてくれる。食事に誘えば食事に来る。ホテルに誘えばホテルに来る。これは大変な世の中です。誘っても断られることがあるから、男女の“交通整理”ができているのです。
ところが、傷つきやすい男性は、最初に出会った女性から傷つけられたら、もう立ち直れません。現代の女性たちは言葉がきつく、相手が二度と立ち上がれないような、きついことを言う人だっています。そういう女性からパシッと言われてしまい、女性不信になってしまう男性がいるのです。
言葉で傷つきやすい人は女性にもいます。男性には特にセクハラに当たるとは思えないような言葉であっても、それで傷つく女性がいます。
実は、自分で自分を傷つけるようなことを考えている人が、それと同じような内容の言葉を他の人から言われたときに、感情の振幅が非常に激しくなって、こたえるようです。そういうことが原因で引きこもっていくのでしょう。
現代は文明の利器が発達していて、引きこもっていても、いろいろな情報を取ることができるので、引きこもりが可能になっている面もあります。
生きていくための力を身につける
ここで考え方を整理しておきましょう。
たいていの人は組織立った動きができ、組織の一員として仕事ができるので、そういう目で見ると、引きこもる人のことが、「明らかに異質で、おかしい」と思えるかもしれません。
しかし、「いや、それは別におかしくないのだ。もともとは、そんなものなのだ」という思いを持たなくてはなりません。
現代社会は、組織立った動きを嫌がる人を、ある程度、仕込んで、他の人たちと同様に動けるようにしてきたのです。しかし、「どうしても従わない人も一部いるのだ」ということは知っておいてください。
引きこもる人のなかには、何らかの方面で自己実現を目指していて、そのために他の人と距離を取りたがる人もいます。その事情を俗世の人は理解できないことが普通なので、その人の周りの人は、「世の中には、こんな人もいるのだ」と思ったほうがよいのです。
また、病的な意味で他の人と接触できない人もいます。そのなかには、霊障(注)と思われる人もいます。
そういう人に対して、絶対に悪意を持たず、悪いことを言わずに接することのできる人が出てくれば、その人は心を開くでしょう。
そんな人が出てこなかった場合は、おそらく、その人の世話をするのは身内ぐらいしかいないと思います。
完全に引きこもって、母親など特定の人以外とは接触しないような人は、身内のだれかに対して無言の抵抗をしている場合がよくあります。何か親子の問題なり兄弟の問題なりがあるのだと思われます。
そういう人は、母親などが生きていて世話をしてくれているあいだは、引きこもりを続けるかもしれませんが、世話をしてくれる人が死んだときには、やはり自立せざるを得なくなります。やがて、そういう時が来るでしょう。
引きこもりを事前に防ぐには、どうすればよいかということですが、子供時代に、ある程度、自立訓練をしておくことが大切でしょう。社会に出て自分で生きていけるようにする訓練を早めに開始しておくことです。
現代社会は管理社会であり、ストレスの多い社会なので、潰れてしまう人がいても不思議ではありません。
したがって、そのなかで生きていくための力を身につけることが必要です。訓練をして、“黴菌”に勝つ力を身につけなくてはなりません。世の中には、黴菌に対する免疫がなく、抵抗力のない人もいるので、「免疫をつける」ということを考える必要もあるのです。
ただ、引きこもるかどうかは、最後は各人の問題です。
繁華街などにホームレスの人がいることもありますが、「昔は、仏教の出家修行者も、あんな感じだったのかな」と思うと、そういう人を責める気が起きてこないものです。
その時代の価値観に合わない人もいますが、価値観の多様性は認めなくてはいけません。それぞれの人に、それぞれの人生修行があるのであり、他の人が窺い知ることのできないところもあるのです。 (了)
2018年7月号 「大人のひきこもり」からの再起
支えられ、やり直せる街づくり / 地域シリーズ神奈川
https://the-liberty.com/article.php?item_id=14483
2015年9月号 不登校はこうすれば解決できる
- 再登校率96%以上の支援スクールが実践する「新常識」
https://the-liberty.com/article.php?item_id=9934
2019年02月18日
受刑者も泣き、本校生徒も泣いた!交流会
SBCニュースワイド キャスターのつぶやきより
http://sbc21.co.jp/blogwp/caster/
投稿日 2019.02.14 19:30
さてきょうのニュースワイドでは、4月から継続取材をさせていただいている、松本少年刑務所桐分校で学ぶ2人の受刑者が、本校の中学生と音楽で交流した様子をお伝えしました。
(注:一人は50代男性で名前が外国のかた、もう一人は20代男性で日本のかた)
澄んだ生徒たちの歌声をききながら、あるいは校長先生の温かいメッセージを受け止め、2人の受刑者の頬に流れた涙。
現場に一緒に同行された刑務所の方も涙を流されている方もいました。
生徒さんで涙を流す子もいて、そんな現場を目の当たりにしいろんなことを感じた濃密な時間になりました。
引き続き卒業の日々までを追っていきたいと思います。(さ) ←(注・アナウンサー三島さやかさん)
2019年02月09日
2018年09月09日
扇風機も無い松本分校で学ぶ受刑者
8月10日20時56分 SBCニュースより
いのちの根を深く~刑務所の中学校~
刑務所内中学校に、50代と20代入学
全国で唯一の刑務所の中の中学校で入学式が行われ、正式な入学者は1人で1955年の開校以来最も少なくなりました。
松本市立旭町中学校桐分校の入学式は松本少年刑務所の体育館で行われました。
今年度の入学者は義務教育を終えていない本科生の50代の外国籍の男性1人で、聴講生の20代の日本国籍の男性とともに式に臨みました。
聴講生制度は義務教育を修了したものの実質的には十分な教育を受けられなかった受刑者を対象に、8年前から導入されています。
中林勝彦学校長は式辞で野口英世が自分の弱点をばねに成長をとげたエピソードを語り、「劣等感と己の弱い心に負けないで頑張ってください」と激励しました。
桐分校は終戦間もない頃、当時の少年刑務所の受刑者の8割ほどが義務教育を終えていなかったことから、更生の意欲を高め社会復帰に必要な知識を身につけることなどを目的に1955年に開校しました。
最も多い年には28人が入学しましたが年々対象の受刑者が減少し、今年の入学者はこれまでで最も少なくなりました。
本科生となった受刑者は「私たちは様々な事情から義務教育である中学校を卒業することができなかったり、卒業はしたものの学ぶ機会が少ないまま今日に至ってしまいました。
そのことはいつも負い目となってきましたし、学力不足から社会でつらい思いもしてきました。
人としても成長していきたいと考えています」と決意の言葉を述べました。
桐分校では中学3年分の課程を1年間で学ぶため、生徒は1日7時間の授業と夜の自習に取り組みます。
参考
松本市立旭町中学校桐分校
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E5%B0%91%E5%B9%B4%E5%88%91%E5%8B%99%E6%89%80
2018年09月07日
不登校予備軍が質問・死んだらどうなるの?
今、夏休みが終わっても、学校に行きたくなくなる生徒が多いようですね~。
NHKシブ5時で、学校に行きたくない生徒の質問に、死んだらどうなるの?とか、学校って何のためにあるの?などを紹介していましたが、これこそ宗教のお家芸ですよね~。
正しい宗教団体に聞けば全て解決しまして、元気に学校へ行くことができるでしょう!
その正しい宗教団体とは、間違いなく「幸福の科学」ですよね~!
NHKさん!意地を張らないで、素直に「幸福の科学」に聞いてみて~!
人は死んだらどうなる?驚きの真実 【霊的世界のほんとうの話】《動画あり》
https://happy-science.jp/info/2016/16493/
いじめ・不登校
人は誰しも、 自分だけの「人生の問題集」をもって生まれてきます。
幸福の科学の教えでその問題集を解き、ほんとうの幸せを見つけてみませんか?
https://happy-science.jp/info/category/lifestory/ijime/
一般財団法人「いじめから子供を守ろうネットワーク」
http://mamoro.org/
自殺防止サイト
https://withyou-hs.net/worry/bullying.html
2018年07月23日
東大卒解けない・小3が作った難問
東大卒芸人・田畑藤本の藤本が頭を抱えたという難問に挑戦。
小学3年生が作ったという問題は、俳句
「◯◯◯◯◯
あああああああ
おおおおお」
の
「◯◯◯◯◯」
に入る言葉を答えよ、というもの。
ヒントは夏の季語。
答えは、
せんぷうき
2018年05月28日
登校率96%!不登校の共通した原因は
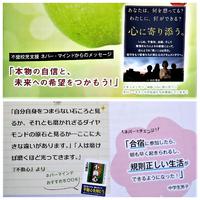
不登校児支援スクール ネバー・マインド
http://hs-nevermind.org/effort/
不登校の共通した原因
・自己評価が低く、自信がない
・人と接するのが嫌で、人を信用できなくなっている
・このままではいけないと思っているが、どうしたらいいのかわからない、やる気がでない
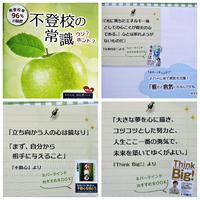
スクールの三つの大事にしている心がけ
一つ目「子供を、白紙の目で見る」
二つ目「子供の光り輝く性質(仏性)を信じ、拝みだす」
三つ目「自助努力の大切さを教える」
2017年05月10日
この信号名読めますか?
答えは、じゃくまく、くいせけ、おんべがわよこた、いもじや、うっさわ。
長野市千曲市は難問漢字地名の宝庫ですね~(笑)
大体、千曲市自体が、千曲市役所がなくて、千曲市更埴庁舎って言うらしいですから~(笑)
ちなみに、長野市川中島の御厨や上氷鉋なども中々刺激的ではあります~(爆)
・・答え・みくりや、かみひがの
2016年01月07日
美術展県代表!高3英検1級合格!テニス優勝!などなど
大学合格他、ものすごいことになってますね~!
クリビツ・テンギョー(びっくりぎょうてん)ですね!(笑)
だいじょうぶですよ!泣いてませんから~(爆)

幸福の科学那須学園・中学・高校
http://happy-science.ac.jp/index.html
2015年12月29日 とちテレ「トップに聞く~トチギのリーダー~」元旦放送予定
2015年12月19日 第3回 ハバロフスク「環太平洋アートフェスティバル 友好と夢展」第3位入賞!
2015年12月17日 第58回栃木県高校美術展 最優秀賞受賞! 栃木県代表作品に選出!
2015年12月04日 高校チアダンス部 JCDA全日本チアダンス選手権全国大会 4位入賞!
2015年12月03日 高校3年生 英検1級に合格!
2015年11月22日 中学チアダンス部 関東ダンスドリル大会団体総合優勝! 全国大会出場へ!
2015年10月24日 高円宮杯英語弁論大会栃木県大会で最優秀賞を受賞!
2015年05月26日 テニス女子ダブルス インターハイ県予選優勝! インターハイ初出場へ2
015年05月13日 男女テニス部 インターハイに向け好発進!北部支部予選会6冠達成!
2015年05月01日 栃木県総合体育大会 テニス女子団体 二年連続優勝!
2015年04月11日 第14回 東北私立高等学校テニス大会 団体初優勝!
2015年04月06日 中学チアダンス部 USA全国大会 総合優勝グランプリ獲得!!
2015年04月06日 チアダンス部世界大会入賞!
クリビツ・テンギョー(びっくりぎょうてん)ですね!(笑)
だいじょうぶですよ!泣いてませんから~(爆)

幸福の科学那須学園・中学・高校
http://happy-science.ac.jp/index.html
2015年12月29日 とちテレ「トップに聞く~トチギのリーダー~」元旦放送予定
2015年12月19日 第3回 ハバロフスク「環太平洋アートフェスティバル 友好と夢展」第3位入賞!
2015年12月17日 第58回栃木県高校美術展 最優秀賞受賞! 栃木県代表作品に選出!
2015年12月04日 高校チアダンス部 JCDA全日本チアダンス選手権全国大会 4位入賞!
2015年12月03日 高校3年生 英検1級に合格!
2015年11月22日 中学チアダンス部 関東ダンスドリル大会団体総合優勝! 全国大会出場へ!
2015年10月24日 高円宮杯英語弁論大会栃木県大会で最優秀賞を受賞!
2015年05月26日 テニス女子ダブルス インターハイ県予選優勝! インターハイ初出場へ2
015年05月13日 男女テニス部 インターハイに向け好発進!北部支部予選会6冠達成!
2015年05月01日 栃木県総合体育大会 テニス女子団体 二年連続優勝!
2015年04月11日 第14回 東北私立高等学校テニス大会 団体初優勝!
2015年04月06日 中学チアダンス部 USA全国大会 総合優勝グランプリ獲得!!
2015年04月06日 チアダンス部世界大会入賞!
2015年10月20日
NHK英会話講師の大間違い!
このネタって、映画UFO学園の秘密・にも確か出てきてたような・・
I wish youが省かれている、祈願文、て~フレ~ズが・・
NHKの講師もこんな程度なので、皆さん自信持ってください~、って、誰に言ってんだろ俺~(笑)
世の中のプロといっても、数年勉強した程度で抜ける
先日も、最近のNHKの英会話の講座を聴いていたら、講師が得意気に「Have a nice day.とか、Have a good day.は、命令文です」と言っていました。これは、「よい一日を」とか「今日もいい日になりますように」というような意味ですが、「これは命令文です。命令文ですけれども、低い声でHave a good day.などと言うと感じが悪く聞こえるので、いちおう明るい声でHave a nice day.と言ってください。つまり、Please have a nice day.の気分で言ってくださいね」と解説していました。
しかし、これが命令文のはずはないのです。私は、幸福の科学学園の中1の英文法入門の最初の講義で、「これは命令文ではありません。これは祈願文です」と書いたのです。
ところが、中学に入ったばかりの人が最初の5分で聴く話なのに、今、現役でやっているNHKの講師が、「命令文だ」と何回も繰り返して教えているのです。しかも類語をたくさん並べて言っているのですが、これは違うのです。
I wish you have a nice day.からHave a nice day.になっているので、I wish youが省かれているのです。ですから、祈願文なのです。
英語では、Have a bad day.という言葉は使いませんし、ありません。なぜかというと、これはそのように希望を述べる言葉だからです。
命令文であればHave a bad day.であっても使えるはずです。しかし、英語にはそのようなものはありません。これは祈願文なのです。
それを幸福の科学学園では中1生が最初に勉強するのですが、今の現役の英語講師は、それを知らずに言っているわけです。 そうしたものに接すると、やはり自信が出ます。
つまり、世の中のプロといっても、このレベルなのです。数年間勉強をし直した程度でも、そのような人を軽々と抜いてしまうことが分かり、自信を持ちました。
【書籍】エイジレス成功法・生涯現役9つの秘訣より
I wish youが省かれている、祈願文、て~フレ~ズが・・
NHKの講師もこんな程度なので、皆さん自信持ってください~、って、誰に言ってんだろ俺~(笑)
世の中のプロといっても、数年勉強した程度で抜ける
先日も、最近のNHKの英会話の講座を聴いていたら、講師が得意気に「Have a nice day.とか、Have a good day.は、命令文です」と言っていました。これは、「よい一日を」とか「今日もいい日になりますように」というような意味ですが、「これは命令文です。命令文ですけれども、低い声でHave a good day.などと言うと感じが悪く聞こえるので、いちおう明るい声でHave a nice day.と言ってください。つまり、Please have a nice day.の気分で言ってくださいね」と解説していました。
しかし、これが命令文のはずはないのです。私は、幸福の科学学園の中1の英文法入門の最初の講義で、「これは命令文ではありません。これは祈願文です」と書いたのです。
ところが、中学に入ったばかりの人が最初の5分で聴く話なのに、今、現役でやっているNHKの講師が、「命令文だ」と何回も繰り返して教えているのです。しかも類語をたくさん並べて言っているのですが、これは違うのです。
I wish you have a nice day.からHave a nice day.になっているので、I wish youが省かれているのです。ですから、祈願文なのです。
英語では、Have a bad day.という言葉は使いませんし、ありません。なぜかというと、これはそのように希望を述べる言葉だからです。
命令文であればHave a bad day.であっても使えるはずです。しかし、英語にはそのようなものはありません。これは祈願文なのです。
それを幸福の科学学園では中1生が最初に勉強するのですが、今の現役の英語講師は、それを知らずに言っているわけです。 そうしたものに接すると、やはり自信が出ます。
つまり、世の中のプロといっても、このレベルなのです。数年間勉強をし直した程度でも、そのような人を軽々と抜いてしまうことが分かり、自信を持ちました。
【書籍】エイジレス成功法・生涯現役9つの秘訣より
2015年08月25日
子育て110番サリバン先生・ヘレン・ケラー(前半)
ヘレン・ケラーの心の扉を開いた サリバン先生の教育(前半)
子育て110番_201505 ハッピー・サイエンス・サイトより、
http://www.are-you-happy.com/article_childrearing/4661

子どもの教育に携わる者にとって、ヘレン・ケラーを教育したサリバン先生は「先生のお手本」のような方です。障害を持つ子供への教育という枠を超え、すべての親と教育者が学ぶべき愛と精神がそこにあります。
サリバン先生は、一体どのようにして暗闇の中にいたヘレンの心の扉を開き、知性の光を与えたのでしょうか。
野獣のような孤独な少女
子供が周りの人や環境から学習しつつ成長するためには、見る力、聴く力というのは不可欠といえるほど重要ですが、ヘレンは、熱病のためにわずか1才半で視力と聴力を失いました。
何の音も聞こえない暗闇の中で、孤独にもがいていた6才のヘレンは、まさに野獣のような子供でした。フォークは床に投げ捨て、ごはんは手づかみで食べ、足りなければ他の人のお皿に手を突っ込む。行動の基準は、やりたいか、やりたくないか。気に入らないものはすべて壊して回り、一度かんしゃくを起こすと地団太を踏んで泣きわめき、誰にも手が付けられなくなる。ちょうどイヤイヤ期ピークの2才児のようでした。
両親であるケラー大尉とやさしいお母さんは、「仕方がない」と思いながらヘレンを甘やかして育てます。けれど、せめて一家の恥にならないように、人並みにごはんを食べ、人様の手を借りずに、人並みに一日を過ごせる人間にしなければならないと考え、呼ばれて来たのがサリバン先生でした。
「わたしの先生」
サリバン先生はまだ二十歳という若さでしたが、ヘレンに出会ってすぐに気づきました。「あなたは知りたいのね。学びたいのね。成長したいのね!」
サリバン先生には、ヘレンの中にある知的欲求がキラキラと輝いて見えました。しかし同時に、教育されていないヘレンには、魂の力のようなものが欠けている、と感じました。
わが子を甘やかして言いなりになる両親からヘレンを引き離し、ふたりで遠くの離れに住み、サリバン先生の教育が始まります。
サリバン先生は、ヘレンがまず「従順さ」を学ばなければ、知識だけでなく愛さえもその魂には入っていかないと考えました。「従順さ」とは、奴隷のように人の言いなりになることではなく、自分より優れた者の存在を認め、その人から素直に教えを学ぶ精神のことです。もちろんヘレンは徹底的に抵抗しました。ナプキンを投げ捨て、サリバン先生を叩き、蹴り、暴れて逃げ回ります。しかし、サリバン先生は決して譲らず、あきらめず、忍耐強くヘレンをしつけます。
「私のかわいいヘレン」「賢く美しいヘレン」――サリバン先生の手紙の中には、ヘレンを愛しく思う言葉がくり返し綴られます。だからこそ厳しく育てるのです。それは、愛ある厳しさです。
わずか二週間で、ヘレンの心に、サリバン先生への強い信頼が生まれます。さらに数週間後、ヘレンは「WATER」(水)という言葉を獲得しました。ヘレンの心に知性と希望の光が差し込みます。外の世界と繋がる扉が開かれたのです。どんなにうれしかったことでしょう。ヘレンは、この忍耐強い恩人を「先生」と呼ぶようになりました。
(次回に続く)
奥田敬子先生 Keiko Okuda
早稲田大学第一文学部哲学科卒業。一男一女の母。
現在、幼児教室エンゼルプランVで1~6歳の幼児200人を指導。
毎クラス15分間の親向け「天使をはぐくむ子育て教室」が好評。
Illustration by Mika Kameo
子育て110番_201505 ハッピー・サイエンス・サイトより、
http://www.are-you-happy.com/article_childrearing/4661

子どもの教育に携わる者にとって、ヘレン・ケラーを教育したサリバン先生は「先生のお手本」のような方です。障害を持つ子供への教育という枠を超え、すべての親と教育者が学ぶべき愛と精神がそこにあります。
サリバン先生は、一体どのようにして暗闇の中にいたヘレンの心の扉を開き、知性の光を与えたのでしょうか。
野獣のような孤独な少女
子供が周りの人や環境から学習しつつ成長するためには、見る力、聴く力というのは不可欠といえるほど重要ですが、ヘレンは、熱病のためにわずか1才半で視力と聴力を失いました。
何の音も聞こえない暗闇の中で、孤独にもがいていた6才のヘレンは、まさに野獣のような子供でした。フォークは床に投げ捨て、ごはんは手づかみで食べ、足りなければ他の人のお皿に手を突っ込む。行動の基準は、やりたいか、やりたくないか。気に入らないものはすべて壊して回り、一度かんしゃくを起こすと地団太を踏んで泣きわめき、誰にも手が付けられなくなる。ちょうどイヤイヤ期ピークの2才児のようでした。
両親であるケラー大尉とやさしいお母さんは、「仕方がない」と思いながらヘレンを甘やかして育てます。けれど、せめて一家の恥にならないように、人並みにごはんを食べ、人様の手を借りずに、人並みに一日を過ごせる人間にしなければならないと考え、呼ばれて来たのがサリバン先生でした。
「わたしの先生」
サリバン先生はまだ二十歳という若さでしたが、ヘレンに出会ってすぐに気づきました。「あなたは知りたいのね。学びたいのね。成長したいのね!」
サリバン先生には、ヘレンの中にある知的欲求がキラキラと輝いて見えました。しかし同時に、教育されていないヘレンには、魂の力のようなものが欠けている、と感じました。
わが子を甘やかして言いなりになる両親からヘレンを引き離し、ふたりで遠くの離れに住み、サリバン先生の教育が始まります。
サリバン先生は、ヘレンがまず「従順さ」を学ばなければ、知識だけでなく愛さえもその魂には入っていかないと考えました。「従順さ」とは、奴隷のように人の言いなりになることではなく、自分より優れた者の存在を認め、その人から素直に教えを学ぶ精神のことです。もちろんヘレンは徹底的に抵抗しました。ナプキンを投げ捨て、サリバン先生を叩き、蹴り、暴れて逃げ回ります。しかし、サリバン先生は決して譲らず、あきらめず、忍耐強くヘレンをしつけます。
「私のかわいいヘレン」「賢く美しいヘレン」――サリバン先生の手紙の中には、ヘレンを愛しく思う言葉がくり返し綴られます。だからこそ厳しく育てるのです。それは、愛ある厳しさです。
わずか二週間で、ヘレンの心に、サリバン先生への強い信頼が生まれます。さらに数週間後、ヘレンは「WATER」(水)という言葉を獲得しました。ヘレンの心に知性と希望の光が差し込みます。外の世界と繋がる扉が開かれたのです。どんなにうれしかったことでしょう。ヘレンは、この忍耐強い恩人を「先生」と呼ぶようになりました。
(次回に続く)
奥田敬子先生 Keiko Okuda
早稲田大学第一文学部哲学科卒業。一男一女の母。
現在、幼児教室エンゼルプランVで1~6歳の幼児200人を指導。
毎クラス15分間の親向け「天使をはぐくむ子育て教室」が好評。
Illustration by Mika Kameo
2015年07月11日
岩手いじめ自殺・いじまも井澤氏語る
岩手いじめ自殺は止められなかったのか? いまだに残る隠ぺい体質
2015.07.09 ザ・リバティ・ウェブより、
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9879

岩手県矢巾(やはば)町で中学2年の男子生徒が、いじめを示唆する内容をノートに記した後、自殺した問題について、同町教育委員会は、いじめの有無を調査する第三者委員会を設置することを決めた。
問題のノートは、毎日担任に提出するもの。この中で男子生徒は、「そろそろ休みたい。氏(死)にたい」「もう市(死)ぬ場所はきまってるんですけどねwまぁいいか」などと書き残していた。
6年間で5000件以上のいじめ相談を受けるいじめ解決の専門家、一般財団法人「いじめから子供を守ろうネットワーク」代表の井澤一明氏は、次のように話す。
「岩手県は、昔ながらの隠ぺい体質が特に色濃く残っている地域です。『声をあげたり、波風を立てる者が悪だ』という空気があります。これまで相談を受けたもののうち、岩手県で解決できなかったいじめ事件は2件ありましたが、ひとつは県の教育委員会が出て来ても『証拠がない』の一点張り、もうひとつは、市議会議員を巻き込んでもなあなあにされてしまいました。今回の事件の背景には、こうした体質があると思います」
「日本全国を見れば、いじめ防止法ができてから、教師や校長の意識は確実に変わってきています。私たちに協力してくれている校長先生からは、ある教育関係者の集まりで、自分の学校の問題を赤裸々に話して、『みなさん知恵をかしてください』と発表する人もいたと聞きました。ただ、私が教師向けの講演をしていて驚くのは、先生たちが『いじめ防止法』の内容をほとんど知らないということです。『いじめ防止法』には教師に対する罰則がないことにも問題があると思います」
「学校の姿勢が変わることが何より重要です。今回、学校側は『いじめを認識していなかった』と言っており、担任の先生の責任が問われていますが、学校の空気として、言い出せない雰囲気ができていたのではないかと思います。担任の先生も周りに相談できずに苦しんでいたのではないでしょうか。校長が変われば学校は変わります。このような痛ましい事件を防ぐためにも、隠ぺい体質を変えなければなりません」
井澤代表は他にも、子供たちに「転校」や「警察に通報する」という選択肢があると知らせることや、「いじめは悪である」という善悪の価値判断を教えていくことなどを訴えた。
【関連サイト】一般財団法人「いじめから子供を守ろうネットワーク」
http://mamoro.org/
2015.07.09 ザ・リバティ・ウェブより、
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9879

岩手県矢巾(やはば)町で中学2年の男子生徒が、いじめを示唆する内容をノートに記した後、自殺した問題について、同町教育委員会は、いじめの有無を調査する第三者委員会を設置することを決めた。
問題のノートは、毎日担任に提出するもの。この中で男子生徒は、「そろそろ休みたい。氏(死)にたい」「もう市(死)ぬ場所はきまってるんですけどねwまぁいいか」などと書き残していた。
6年間で5000件以上のいじめ相談を受けるいじめ解決の専門家、一般財団法人「いじめから子供を守ろうネットワーク」代表の井澤一明氏は、次のように話す。
「岩手県は、昔ながらの隠ぺい体質が特に色濃く残っている地域です。『声をあげたり、波風を立てる者が悪だ』という空気があります。これまで相談を受けたもののうち、岩手県で解決できなかったいじめ事件は2件ありましたが、ひとつは県の教育委員会が出て来ても『証拠がない』の一点張り、もうひとつは、市議会議員を巻き込んでもなあなあにされてしまいました。今回の事件の背景には、こうした体質があると思います」
「日本全国を見れば、いじめ防止法ができてから、教師や校長の意識は確実に変わってきています。私たちに協力してくれている校長先生からは、ある教育関係者の集まりで、自分の学校の問題を赤裸々に話して、『みなさん知恵をかしてください』と発表する人もいたと聞きました。ただ、私が教師向けの講演をしていて驚くのは、先生たちが『いじめ防止法』の内容をほとんど知らないということです。『いじめ防止法』には教師に対する罰則がないことにも問題があると思います」
「学校の姿勢が変わることが何より重要です。今回、学校側は『いじめを認識していなかった』と言っており、担任の先生の責任が問われていますが、学校の空気として、言い出せない雰囲気ができていたのではないかと思います。担任の先生も周りに相談できずに苦しんでいたのではないでしょうか。校長が変われば学校は変わります。このような痛ましい事件を防ぐためにも、隠ぺい体質を変えなければなりません」
井澤代表は他にも、子供たちに「転校」や「警察に通報する」という選択肢があると知らせることや、「いじめは悪である」という善悪の価値判断を教えていくことなどを訴えた。
【関連サイト】一般財団法人「いじめから子供を守ろうネットワーク」
http://mamoro.org/
2015年05月19日
子育て110番・習い事選び
子育て110番 水泳、ピアノ、英会話etc.…… 子どもには何を習わせるのがいいでしょうか? 習い事選びのポイントを教えてください
ハッピー・サイエンス・サイトより、抜粋・編集

選択肢の多さがいちばんの悩み
子どもが3、4才になると、多くの親御さんが「何かひとつくらい習い事をさせようか」と考え始めます。近年の習い事人気ランキング不動のトップ3は「水泳」「ピアノ」「英会話」、それに次いでリトミックや体操、学習塾が人気です。ほかにも、サッカー、ダンス、書道、そろばん、空手など、人気の習い事はたくさんあります。また、今年のように冬季オリンピックで日本人選手が活躍すると、マイナースポーツと言われるスケートやスキー、スノーボードにも注目が集まりますね。これだけいろいろな選択肢があると、親としては、何を習わせるかがいちばんの悩みの種になります。
まず、習い事を選ぶときのポイントとして親が考えるのは、①うちの子に合っているかどうか。②子どもの心身や頭脳の成長に役立つかどうか。③将来の仕事などの役に立つかどうか。④通える範囲に適当な教室があるか。⑤うちの経済状況で続けることができるかどうか。これらのことが判断の材料になるかと思います。
どれもこれも魅力的
人気第1位の水泳は、関節に負担の少ない全身運動で、心肺機能が高まり皮膚も丈夫になるといわれます。小学校で困らないために、泳げるようにしてあげたいという親心も働きます。
ピアノは、目、耳、指、頭脳を同時に使うので、賢い子になるといわれていますし、絶対音感は幼少期にしか備わらないと聞くと、早いうちに習わせなくちゃと焦りもします。
また、これからの時代、どんな職業に就いても英会話は必須だから、できればバイリンガルに育てたい。でも、幼少期の英語レッスンは役に立たない、受験英語習得の妨げになる場合もあるともいわれています。
学校でいじめに遭わないように、空手も習わせたい。学習塾にも通わせたい。ダンスやリトミックもいい……。
一体どれにすればいいの?
決め手は「楽しい!」
スキージャンプは、たいていの人が「こわい」と感じるスポーツでしょうが、高梨沙羅選手は、小さいころに初めて飛んだとき、「楽しい! またやりたい!」と思ったそうです。これこそが、その子の持つ資質であり、可能性です。
子どもは、大人のように「将来のため」とか「成長に役立つかどうか」などと合理的には考えません。「つまらない」と感じるものには興味も意欲もわかず、能力もたいして伸びません。親が無理やりやらせても効果は少ないということです。
反対に、「楽しい! わくわくする!」と感じるものには、幼くても素晴らしい集中力や根気を見せ、わずか10分間でも驚くべき成長を遂げます。ただし興味関心がすぐにほかへ移っていくのもまた、子どもの自然な姿です。
習い事は、親が焦ったり気合を入れすぎたりすると失敗しやすいものです。また、時期が早すぎても、子どもに失敗体験を与えるだけに終わります。親は、まずは子どもに体験の機会を与えて、一歩退いたところから「うちの子、 楽しそうかな? わくわくしてるかな?」と、子どもの心の様子や目の輝きなどを観察してみてあげてください。答えは、子どもの瞳の中にあります。
奥田敬子Keiko Okuda
ハッピー・サイエンス・サイトより、抜粋・編集

選択肢の多さがいちばんの悩み
子どもが3、4才になると、多くの親御さんが「何かひとつくらい習い事をさせようか」と考え始めます。近年の習い事人気ランキング不動のトップ3は「水泳」「ピアノ」「英会話」、それに次いでリトミックや体操、学習塾が人気です。ほかにも、サッカー、ダンス、書道、そろばん、空手など、人気の習い事はたくさんあります。また、今年のように冬季オリンピックで日本人選手が活躍すると、マイナースポーツと言われるスケートやスキー、スノーボードにも注目が集まりますね。これだけいろいろな選択肢があると、親としては、何を習わせるかがいちばんの悩みの種になります。
まず、習い事を選ぶときのポイントとして親が考えるのは、①うちの子に合っているかどうか。②子どもの心身や頭脳の成長に役立つかどうか。③将来の仕事などの役に立つかどうか。④通える範囲に適当な教室があるか。⑤うちの経済状況で続けることができるかどうか。これらのことが判断の材料になるかと思います。
どれもこれも魅力的
人気第1位の水泳は、関節に負担の少ない全身運動で、心肺機能が高まり皮膚も丈夫になるといわれます。小学校で困らないために、泳げるようにしてあげたいという親心も働きます。
ピアノは、目、耳、指、頭脳を同時に使うので、賢い子になるといわれていますし、絶対音感は幼少期にしか備わらないと聞くと、早いうちに習わせなくちゃと焦りもします。
また、これからの時代、どんな職業に就いても英会話は必須だから、できればバイリンガルに育てたい。でも、幼少期の英語レッスンは役に立たない、受験英語習得の妨げになる場合もあるともいわれています。
学校でいじめに遭わないように、空手も習わせたい。学習塾にも通わせたい。ダンスやリトミックもいい……。
一体どれにすればいいの?
決め手は「楽しい!」
スキージャンプは、たいていの人が「こわい」と感じるスポーツでしょうが、高梨沙羅選手は、小さいころに初めて飛んだとき、「楽しい! またやりたい!」と思ったそうです。これこそが、その子の持つ資質であり、可能性です。
子どもは、大人のように「将来のため」とか「成長に役立つかどうか」などと合理的には考えません。「つまらない」と感じるものには興味も意欲もわかず、能力もたいして伸びません。親が無理やりやらせても効果は少ないということです。
反対に、「楽しい! わくわくする!」と感じるものには、幼くても素晴らしい集中力や根気を見せ、わずか10分間でも驚くべき成長を遂げます。ただし興味関心がすぐにほかへ移っていくのもまた、子どもの自然な姿です。
習い事は、親が焦ったり気合を入れすぎたりすると失敗しやすいものです。また、時期が早すぎても、子どもに失敗体験を与えるだけに終わります。親は、まずは子どもに体験の機会を与えて、一歩退いたところから「うちの子、 楽しそうかな? わくわくしてるかな?」と、子どもの心の様子や目の輝きなどを観察してみてあげてください。答えは、子どもの瞳の中にあります。
奥田敬子Keiko Okuda
2015年05月13日
幸福の科学学園式勉強法公開
【中高生編】「知」「情」「意」が魅力ある人をつくる! 世界にはばたく子供の育て方

夢を明確にし、志を立てることが「知」のモチベーションになる
幸福の科学学園では、入学するとまず自分の「夢」や「目標」を明確にして「志」を立てます。何のために勉強するのかを明確にすることで、「知」のモチベーションが上がるんですね。学園では廊下を歩きながら参考書を読んだり、食堂に並ぶ時間も英単語帳を見るなど、細切れの時間を使って勉強する生徒の姿が多く見られます。新入生も、先輩たちのそういう姿を見て「知」の大切さを学んでいきます。
学園では、世界で活躍する人材の育成、を目指しているので、特に英語教育に力を入れています。中学ではオーストラリア、高校ではアメリカへ、全生徒が語学研修に行きます。英検が近くなると、学年を越えて級ごとに「英検大勝利講座」という補講を行っており、中学1年生で準1級に合格した生徒も出ました。
那須本校では、開校から3年連続で、東大合格者2名を出し、今年は京大2名、早稲田33名を輩出。栃木県トップレベルの進学校に成長したのは、「知」に向かう「学」の柱がしっかりできているからなのです。
「宗教科」の授業と寮での共同生活が「愛ある秀才」を育てる
一般的に、偏差値が上がれば上がるほどセルフィッシュ(自己中心的)になる傾向があるといいます。でも、幸福の科学の「与える愛」の教えを学んでいる学園の生徒たちは、偏差値が上がるほどに「愛ある人になろう」と努力しているように感じられます。ここが、ほかの進学校とは明らかに違うところですね。
「情」を育むいちばんの機会は、週に1~2回ある宗教科の授業です。授業では、「報恩の思いを持ち、仕事を通じて社会貢献をする、それが学園生の使命なのだ」ということを教えています。ですので生徒たちは、感謝の思いがとても強いのです。学力を伸ばすことだけが大事なのではない、勉強だけやっていても、自分の使命を果たすには至らないんだということを、生徒たちはよく知っているのでしょう。
もうひとつは、ほとんどの生徒が寮生活を送るという環境です。高校2年生までは2~4人部屋での共同生活なので、助け合う精神が必要となります。日々の共同生活のなかで、与える愛を実践し、絆を深め、団結の大切さを学び、「情」が育まれていくのです。生徒たちは、みんなとても個性的。そして生徒たちは、それぞれの個性や強みを尊重し、お互いに認め合っています。「愛ある秀才」がたくさん育つ、それが幸福の科学学園の大きな特徴といえます。
「探究創造科」の授業と1日のタイトなスケジュールの中で強い「意」の力が身につく
学園では、クリエイティブな人材や、新時代を創造するリーダーを養成するための「探究創造科」という授業の中で、資本主義の精神を学んだり、新しいものを自分で発明・発見する力を養います。新しいものを生み出すときに必要な「強い意志の力」が、ここで必然と身についていきます。受験秀才にありがちな優柔不断さとは無縁なのが、幸福の科学学園の生徒なのです。
学園生は、日々の生活の中でも意志の力が鍛えられます。学園では、朝6時半の起床から夜11時の就寝時間まで、かなりタイトなスケジュール。自分の時間がほとんどない中で、部屋の掃除や洗濯など身の回りのこともしなければならないので、自分を律する力、強い意志の力がなければ、学園での生活はできません。
「意志の力」というのは、先天的なものではなく後天的に養われていく部分。そう考えると、学園生は毎日の生活のなかで、意志の力が鍛えられていくのですね。意志の強さはときとして頑固さにつながることがありますが、学園生たちを見ていると、頑固さによって人を傷つけたり、迷惑をかけたりといったことがありません。それはきっと「情」の部分がしっかり培われているからなのだと思います。
竜の口法子 ハッピー・サイエンス・サイトより、抜粋・編集

夢を明確にし、志を立てることが「知」のモチベーションになる
幸福の科学学園では、入学するとまず自分の「夢」や「目標」を明確にして「志」を立てます。何のために勉強するのかを明確にすることで、「知」のモチベーションが上がるんですね。学園では廊下を歩きながら参考書を読んだり、食堂に並ぶ時間も英単語帳を見るなど、細切れの時間を使って勉強する生徒の姿が多く見られます。新入生も、先輩たちのそういう姿を見て「知」の大切さを学んでいきます。
学園では、世界で活躍する人材の育成、を目指しているので、特に英語教育に力を入れています。中学ではオーストラリア、高校ではアメリカへ、全生徒が語学研修に行きます。英検が近くなると、学年を越えて級ごとに「英検大勝利講座」という補講を行っており、中学1年生で準1級に合格した生徒も出ました。
那須本校では、開校から3年連続で、東大合格者2名を出し、今年は京大2名、早稲田33名を輩出。栃木県トップレベルの進学校に成長したのは、「知」に向かう「学」の柱がしっかりできているからなのです。
「宗教科」の授業と寮での共同生活が「愛ある秀才」を育てる
一般的に、偏差値が上がれば上がるほどセルフィッシュ(自己中心的)になる傾向があるといいます。でも、幸福の科学の「与える愛」の教えを学んでいる学園の生徒たちは、偏差値が上がるほどに「愛ある人になろう」と努力しているように感じられます。ここが、ほかの進学校とは明らかに違うところですね。
「情」を育むいちばんの機会は、週に1~2回ある宗教科の授業です。授業では、「報恩の思いを持ち、仕事を通じて社会貢献をする、それが学園生の使命なのだ」ということを教えています。ですので生徒たちは、感謝の思いがとても強いのです。学力を伸ばすことだけが大事なのではない、勉強だけやっていても、自分の使命を果たすには至らないんだということを、生徒たちはよく知っているのでしょう。
もうひとつは、ほとんどの生徒が寮生活を送るという環境です。高校2年生までは2~4人部屋での共同生活なので、助け合う精神が必要となります。日々の共同生活のなかで、与える愛を実践し、絆を深め、団結の大切さを学び、「情」が育まれていくのです。生徒たちは、みんなとても個性的。そして生徒たちは、それぞれの個性や強みを尊重し、お互いに認め合っています。「愛ある秀才」がたくさん育つ、それが幸福の科学学園の大きな特徴といえます。
「探究創造科」の授業と1日のタイトなスケジュールの中で強い「意」の力が身につく
学園では、クリエイティブな人材や、新時代を創造するリーダーを養成するための「探究創造科」という授業の中で、資本主義の精神を学んだり、新しいものを自分で発明・発見する力を養います。新しいものを生み出すときに必要な「強い意志の力」が、ここで必然と身についていきます。受験秀才にありがちな優柔不断さとは無縁なのが、幸福の科学学園の生徒なのです。
学園生は、日々の生活の中でも意志の力が鍛えられます。学園では、朝6時半の起床から夜11時の就寝時間まで、かなりタイトなスケジュール。自分の時間がほとんどない中で、部屋の掃除や洗濯など身の回りのこともしなければならないので、自分を律する力、強い意志の力がなければ、学園での生活はできません。
「意志の力」というのは、先天的なものではなく後天的に養われていく部分。そう考えると、学園生は毎日の生活のなかで、意志の力が鍛えられていくのですね。意志の強さはときとして頑固さにつながることがありますが、学園生たちを見ていると、頑固さによって人を傷つけたり、迷惑をかけたりといったことがありません。それはきっと「情」の部分がしっかり培われているからなのだと思います。
竜の口法子 ハッピー・サイエンス・サイトより、抜粋・編集




