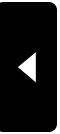2015年11月06日
病気を治す医療と心の力
アー・ユー・ハッピーサイトより、抜粋・編集
2015・12月号
http://www.are-you-happy.com/eudaemonics/4837

〈質問〉
私は眼科のクリニックを経営しています。先般、フランスで開催された国際臨死体験学会に参加してきたのですが、欧米のドクターたちは、死後の世界や魂の存在はもはや否定できないとして、科学的にアプローチしていく段階まで進んでいます。そうした流れのなか、唯物論が大をなしている日本において、今後、次世代の医療者に向け、また、私たち医療者が腰を据えてやるべきことは何か、御教授いただければと思います。
医療の分野の唯物論問題
医療の分野に関しては、当然、唯物論の問題が出てきます。現実に、医者といえども、薬や機械がなかったら何もできないというのはそのとおりで、一応、薬や機械などがあると、何か戦える感じにはなります。ですから、唯物論を完全に否定して、医学系が成り立つかといったら、難しいものはあると思います。武器は武器なのでしょう。ただ、私はそうしたことを否定しているわけではないのです。医療機械を作る人も、いろいろ実験を重ね、より良くなるよう、それらに智慧を加えているということはあるわけです。智慧の結晶として医療機械が作られている場合もありますし、薬もいろいろな実験を重ねた上で「効果がある」というものを出してきているわけですから、まったくそれを否定する気はないのです。
しかし、教育を受ける過程において、やはり唯物論的になり、それ以外のことを言わなくなる傾向があって、極めて、占い師が断定的に言うような言い方をする医者が、薬剤師も含めて多いのです。「もう一生治りません」とか、「この薬は死ぬまで飲んでもらわないと駄目です」などと言うケースがありますが、「勝手に決めないでくれ」と思うところはあります(会場笑)。
反旗を翻す医師たちの出現
しかし最近は、医者のなかでも、反旗を翻している人が本をたくさん出し始めています。多分、底流ではうちの本などの影響をかなり受けているのかもしれません。ガンは切らないほうがいいとか、切って痛い思いをし、抗ガン剤を打たれて苦しみながら死んでいくのと、どうせ死ぬのだったら、痛くもなくてきれいに自宅で死ぬほうがよほどよいのではないか、といった考えも出ています。あるいは、「三日間ご飯を食べずに寝ていれば治る」と言い出す医者も出てきています。
あるいは、西洋の諺である「一日三食のうち、二食は自分のため、一食は医者のため」というのまで出してきている人もいます(会場笑)。要するに、二食食べれば病気にならないが、三食食べたら医者にかからなくてはならなくなる、ということです。このように諺まであるわけですが、中年以降は、そうした過剰摂取、食べ過ぎで病気になるケースは多いです。これは、オーバーカロリーと運動不足で起きており、実際にそういうことはあります。
宗教的奇跡がのぞむ場合の理由
オーバーカロリーにしても運動量にしても、これもある意味では唯物論的に計算できる部分もあるので、そうしたことも絡めた上で、人間の意思をどのようにコントロールし、習慣をつくるか、という問題だと思うのです。
ですから、宗教ができることとしては、ときどき当教団のさまざまな精舎で起きているように、奇跡のように病気を治せる場合もありますけれども、全部が全部治せるわけではありません。どのような恩寵があってその人が治るのか、ということについては、人それぞれに理由があると思うのです。
今まで、「カルマ・リーディング」的なものをやってきましたが、その方がそうした病気や特殊な状態になっている場合、「その理由はこれです」ということを、私が過去世リーディングまでして言い当てた場合は、ほぼ百パーセント治っています。職員も全部、治っているわけです。
2015・12月号
http://www.are-you-happy.com/eudaemonics/4837

〈質問〉
私は眼科のクリニックを経営しています。先般、フランスで開催された国際臨死体験学会に参加してきたのですが、欧米のドクターたちは、死後の世界や魂の存在はもはや否定できないとして、科学的にアプローチしていく段階まで進んでいます。そうした流れのなか、唯物論が大をなしている日本において、今後、次世代の医療者に向け、また、私たち医療者が腰を据えてやるべきことは何か、御教授いただければと思います。
医療の分野の唯物論問題
医療の分野に関しては、当然、唯物論の問題が出てきます。現実に、医者といえども、薬や機械がなかったら何もできないというのはそのとおりで、一応、薬や機械などがあると、何か戦える感じにはなります。ですから、唯物論を完全に否定して、医学系が成り立つかといったら、難しいものはあると思います。武器は武器なのでしょう。ただ、私はそうしたことを否定しているわけではないのです。医療機械を作る人も、いろいろ実験を重ね、より良くなるよう、それらに智慧を加えているということはあるわけです。智慧の結晶として医療機械が作られている場合もありますし、薬もいろいろな実験を重ねた上で「効果がある」というものを出してきているわけですから、まったくそれを否定する気はないのです。
しかし、教育を受ける過程において、やはり唯物論的になり、それ以外のことを言わなくなる傾向があって、極めて、占い師が断定的に言うような言い方をする医者が、薬剤師も含めて多いのです。「もう一生治りません」とか、「この薬は死ぬまで飲んでもらわないと駄目です」などと言うケースがありますが、「勝手に決めないでくれ」と思うところはあります(会場笑)。
反旗を翻す医師たちの出現
しかし最近は、医者のなかでも、反旗を翻している人が本をたくさん出し始めています。多分、底流ではうちの本などの影響をかなり受けているのかもしれません。ガンは切らないほうがいいとか、切って痛い思いをし、抗ガン剤を打たれて苦しみながら死んでいくのと、どうせ死ぬのだったら、痛くもなくてきれいに自宅で死ぬほうがよほどよいのではないか、といった考えも出ています。あるいは、「三日間ご飯を食べずに寝ていれば治る」と言い出す医者も出てきています。
あるいは、西洋の諺である「一日三食のうち、二食は自分のため、一食は医者のため」というのまで出してきている人もいます(会場笑)。要するに、二食食べれば病気にならないが、三食食べたら医者にかからなくてはならなくなる、ということです。このように諺まであるわけですが、中年以降は、そうした過剰摂取、食べ過ぎで病気になるケースは多いです。これは、オーバーカロリーと運動不足で起きており、実際にそういうことはあります。
宗教的奇跡がのぞむ場合の理由
オーバーカロリーにしても運動量にしても、これもある意味では唯物論的に計算できる部分もあるので、そうしたことも絡めた上で、人間の意思をどのようにコントロールし、習慣をつくるか、という問題だと思うのです。
ですから、宗教ができることとしては、ときどき当教団のさまざまな精舎で起きているように、奇跡のように病気を治せる場合もありますけれども、全部が全部治せるわけではありません。どのような恩寵があってその人が治るのか、ということについては、人それぞれに理由があると思うのです。
今まで、「カルマ・リーディング」的なものをやってきましたが、その方がそうした病気や特殊な状態になっている場合、「その理由はこれです」ということを、私が過去世リーディングまでして言い当てた場合は、ほぼ百パーセント治っています。職員も全部、治っているわけです。
2015年10月13日
食物アレルギーの娘が完治した記録
食物アレルギーの娘―必要な栄養は親の愛だった
ボイシーサイトより、抜粋・編集 2015.09.01
http://voicee.jp/2015090111342

Nさん(女性)
長女のMが生後半年の頃。それまでの母乳から、初めて粉ミルクを与えた直後のことです。
ミルクを吐き出し、私の腕の中で息も絶え絶えな愛娘の様子に、すぐさま病院に駆け込みました。
「娘さんは、食物アレルギーのようですね」
私達夫婦はアトピー性皮膚炎を患っていて、Mも生まれた時から肌の弱い子でした。
しかも食物アレルギーを引き起こすと言われる、三大アレルゲン(卵・牛乳・大豆)のすべてに反応すると言うのです。
ミルクをアレルギー疾患用に代え、離乳食の食材も成分表示を見て、慎重に選びます。それでも、一度大丈夫だった食材からもじんましんや湿疹が出てしまうことがあり、安心できません。
食事の30分前には、アレルギーを抑える薬を欠かさず飲ませなくてはなりません。
Mが3歳になると、ようやく医師から「もういいですよ」と、食材の制約が取れました。
私は嬉しくてたまりませんでした。
そんな期待に反し、食卓に初めて出す料理にMは手をつけようともしませんでした。食も細く、幼稚園の小さなお弁当も、いつも残してきます。
この頃は、生まれたばかりの妹のKの面倒をみながら、Mの食事にも気を遣い、正直、数倍手間も時間もかかりました。
「お姉ちゃんなんだから、しっかりしてよ。もうアレルギーを気にしないで、何でも食べられるはずなのに、何で食べないのよ!」
Kが幼稚園に上がり、ある日、幸福の科学の友人にMのことを話してみました。
「あら、それは良かったじゃない!元気だったら、少しくらい食べなくても、病気しないだけでもありがたいわよね」
ドキッとしました。とても大事なことを言われた気がしたのです。
いつものようにお弁当を残してきたことで注意をしたら、「ママは、Kちゃんばっかり!」と、目を真っ赤にして、部屋を飛び出していったMの姿でした。
この時、Mの「寂しい!」という気持ちが私の胸にダイレクトに伝わってきたのです。
「お料理に手をつけなかったのも、Mなりのサインだったのかもしれない。やっぱり寂しかったんだ……」
食べないのはMのワガママだと思っていました。けれど、本当は愛して欲しいことを上手に表せなかったために、私に気持ちを向けて欲しいというサインとして、症状が出ていたのかもしれません。
そして、もう一つ気づいたことがありました。
私は、医師からOKが出たとたんに、遅れた分を取り戻そうと「あれも食べなさい」「これも食べなさい」と急かせていました。それが子どもへの愛だと思っていたのです。
「Mの中ではまだOKではなかったんだ。Mは、私が手間ひまかけて料理に気を遣うより、側にいて抱きしめて欲しかったんだ。もっともっと愛して欲しかったんだね……」
Mの気持ちが伝わってきて、申し訳ない気持ちがあふれてきました。
私は、Mにきちんと向き合い、愛していることをしっかり表現していこうと思いました。
「Mちゃん、すごいね。今日はいつもより多く食べたのね。がんばったね」
そう口に出して褒めてあげるようにすると、「ママ見て!」と嬉しそうに空のお皿を見せにきてくれるようになりました。
スキンシップを多くすると、Mの表情がハツラツとしてきて、短期間のうちに、みるみる変化が現れてきたのです。
それからは食欲も出てきて、1年生の1学期は給食を残すことも多かったMが、3学期にはほとんど全部食べられるようになったのです。
皮膚症状もどんどん良くなり、時々、唇が腫れることはありますが、激しい症状が現れることはなくなりました。
心をこめてMを愛そうと決意しただけなのにこの変化。親の影響力はすごいものだとつくづく感じます。
Mを見ていると、「子どもは親の愛情をエネルギーとして生きているんだ」と本当に思います。
私は、時間をかけ食事に配慮することで、一生懸命に愛を与えていたつもりでしたが、子どもの気持ちを受け止め思いやってあげてこそ、本当の愛なのだとわかりました。
ボイシーサイトより、抜粋・編集 2015.09.01
http://voicee.jp/2015090111342

Nさん(女性)
長女のMが生後半年の頃。それまでの母乳から、初めて粉ミルクを与えた直後のことです。
ミルクを吐き出し、私の腕の中で息も絶え絶えな愛娘の様子に、すぐさま病院に駆け込みました。
「娘さんは、食物アレルギーのようですね」
私達夫婦はアトピー性皮膚炎を患っていて、Mも生まれた時から肌の弱い子でした。
しかも食物アレルギーを引き起こすと言われる、三大アレルゲン(卵・牛乳・大豆)のすべてに反応すると言うのです。
ミルクをアレルギー疾患用に代え、離乳食の食材も成分表示を見て、慎重に選びます。それでも、一度大丈夫だった食材からもじんましんや湿疹が出てしまうことがあり、安心できません。
食事の30分前には、アレルギーを抑える薬を欠かさず飲ませなくてはなりません。
Mが3歳になると、ようやく医師から「もういいですよ」と、食材の制約が取れました。
私は嬉しくてたまりませんでした。
そんな期待に反し、食卓に初めて出す料理にMは手をつけようともしませんでした。食も細く、幼稚園の小さなお弁当も、いつも残してきます。
この頃は、生まれたばかりの妹のKの面倒をみながら、Mの食事にも気を遣い、正直、数倍手間も時間もかかりました。
「お姉ちゃんなんだから、しっかりしてよ。もうアレルギーを気にしないで、何でも食べられるはずなのに、何で食べないのよ!」
Kが幼稚園に上がり、ある日、幸福の科学の友人にMのことを話してみました。
「あら、それは良かったじゃない!元気だったら、少しくらい食べなくても、病気しないだけでもありがたいわよね」
ドキッとしました。とても大事なことを言われた気がしたのです。
いつものようにお弁当を残してきたことで注意をしたら、「ママは、Kちゃんばっかり!」と、目を真っ赤にして、部屋を飛び出していったMの姿でした。
この時、Mの「寂しい!」という気持ちが私の胸にダイレクトに伝わってきたのです。
「お料理に手をつけなかったのも、Mなりのサインだったのかもしれない。やっぱり寂しかったんだ……」
食べないのはMのワガママだと思っていました。けれど、本当は愛して欲しいことを上手に表せなかったために、私に気持ちを向けて欲しいというサインとして、症状が出ていたのかもしれません。
そして、もう一つ気づいたことがありました。
私は、医師からOKが出たとたんに、遅れた分を取り戻そうと「あれも食べなさい」「これも食べなさい」と急かせていました。それが子どもへの愛だと思っていたのです。
「Mの中ではまだOKではなかったんだ。Mは、私が手間ひまかけて料理に気を遣うより、側にいて抱きしめて欲しかったんだ。もっともっと愛して欲しかったんだね……」
Mの気持ちが伝わってきて、申し訳ない気持ちがあふれてきました。
私は、Mにきちんと向き合い、愛していることをしっかり表現していこうと思いました。
「Mちゃん、すごいね。今日はいつもより多く食べたのね。がんばったね」
そう口に出して褒めてあげるようにすると、「ママ見て!」と嬉しそうに空のお皿を見せにきてくれるようになりました。
スキンシップを多くすると、Mの表情がハツラツとしてきて、短期間のうちに、みるみる変化が現れてきたのです。
それからは食欲も出てきて、1年生の1学期は給食を残すことも多かったMが、3学期にはほとんど全部食べられるようになったのです。
皮膚症状もどんどん良くなり、時々、唇が腫れることはありますが、激しい症状が現れることはなくなりました。
心をこめてMを愛そうと決意しただけなのにこの変化。親の影響力はすごいものだとつくづく感じます。
Mを見ていると、「子どもは親の愛情をエネルギーとして生きているんだ」と本当に思います。
私は、時間をかけ食事に配慮することで、一生懸命に愛を与えていたつもりでしたが、子どもの気持ちを受け止め思いやってあげてこそ、本当の愛なのだとわかりました。
2015年09月28日
最近急に体調良好!の原因を探る
まだまだ油断は禁物ですけど、今月25日頃から、急にからだの元から変わってくるのが分かりまして、いつもの症状の、眼精疲労や、めまい、体のだるさ、などがなくなりまして、雨上がりのあとに、陽光がサ~っと差し込んでくるような気分で、ス~っと元から元気が沸いてくるんです。
何で?・・
その原因を探ってみました。
医者には、体の中に雑菌がいると言われましたが、原因は不明のままだったのです。
そして、漢方を数種類服用していました。でも、それ以上良くはなりません。
いつ何時、急に吐き続けてしまうか分かりませんので、怖くて、今でも、抗生物質を手放しませんし、実際、ヤバそうなときには直ぐに服用していました。
最近始めたことや良くなった原因として考えられる事は、
1 サントリー、プロディアという植物性乳酸菌サプリの服用。(プロテクト乳酸菌でからだを守る)
2 エポラのミドリムシサプリの服用。(栄養バランス)
3 自然治癒力のサブリミナルCDの拝聴。(メンタル力強化)
4 緑茶を飲み始める。(消毒作用、雑菌対策)
5 栄養ドリンクを少量づつ服用。(滋養強壮、栄養補給)
6 本格的なうなぎを食べた。(栄養)
7 抱き枕を常用する。(精神安定)
8 首の位置や姿勢を正す。(血流改善)
9 天然石の活用(浄化作用)
10 憑依霊が外れる?(最近亡くなった友人などを諭す)
11 しっかり浴槽に入り、汗をかき、首を温める。(血流改善)
12 腹巻の常時着用(冷え防止)
13 帽子の常時着用(ボケ帽子)(爆)
14 就寝時のネックウォーマー着用
※10は、死後の世界の説明の出来る人は限られていますので、どうも、私を頼って霊が何人か来ている感じがしていましたので、死後の世界のことや、これからどうしたらいいのかなど、わかり易く、ひとり言のように話して聞かせました。おそらく、分かって頂けたと自負していますです~(笑)
この中から、何が一番効果的であったのかを探し出すのは、刑事フォイルでも至難の技でしょうかね~(笑)
私は、激的に変わったのは、微妙にそれぞれが関係してはいるんでしょうけれども、乳酸菌サプリの服用と緑茶の飲用と姿勢、ではないかと思っています。
ほかには、免疫力を高めるといわれています食材、うめぼし、にら、納豆、バナナ、かぼちゃなども毎日のように食べていましたけど・・。
このまま、どんどん回復してくれるとありがたいのですが、暫くは様子見でしょうかね、ですから抗生物質は、まだまだ手放せませんです~(笑)

何で?・・
その原因を探ってみました。
医者には、体の中に雑菌がいると言われましたが、原因は不明のままだったのです。
そして、漢方を数種類服用していました。でも、それ以上良くはなりません。
いつ何時、急に吐き続けてしまうか分かりませんので、怖くて、今でも、抗生物質を手放しませんし、実際、ヤバそうなときには直ぐに服用していました。
最近始めたことや良くなった原因として考えられる事は、
1 サントリー、プロディアという植物性乳酸菌サプリの服用。(プロテクト乳酸菌でからだを守る)
2 エポラのミドリムシサプリの服用。(栄養バランス)
3 自然治癒力のサブリミナルCDの拝聴。(メンタル力強化)
4 緑茶を飲み始める。(消毒作用、雑菌対策)
5 栄養ドリンクを少量づつ服用。(滋養強壮、栄養補給)
6 本格的なうなぎを食べた。(栄養)
7 抱き枕を常用する。(精神安定)
8 首の位置や姿勢を正す。(血流改善)
9 天然石の活用(浄化作用)
10 憑依霊が外れる?(最近亡くなった友人などを諭す)
11 しっかり浴槽に入り、汗をかき、首を温める。(血流改善)
12 腹巻の常時着用(冷え防止)
13 帽子の常時着用(ボケ帽子)(爆)
14 就寝時のネックウォーマー着用
※10は、死後の世界の説明の出来る人は限られていますので、どうも、私を頼って霊が何人か来ている感じがしていましたので、死後の世界のことや、これからどうしたらいいのかなど、わかり易く、ひとり言のように話して聞かせました。おそらく、分かって頂けたと自負していますです~(笑)
この中から、何が一番効果的であったのかを探し出すのは、刑事フォイルでも至難の技でしょうかね~(笑)
私は、激的に変わったのは、微妙にそれぞれが関係してはいるんでしょうけれども、乳酸菌サプリの服用と緑茶の飲用と姿勢、ではないかと思っています。
ほかには、免疫力を高めるといわれています食材、うめぼし、にら、納豆、バナナ、かぼちゃなども毎日のように食べていましたけど・・。
このまま、どんどん回復してくれるとありがたいのですが、暫くは様子見でしょうかね、ですから抗生物質は、まだまだ手放せませんです~(笑)

2015年07月21日
天皇陛下の心臓手術を成功させた天野医師
国際派日本人養成講座より
天皇陛下の執刀医、天野篤の「医師道」
なんとしても患者を救うという使命感と報恩の心が「医師道」の原動力。
78歳の天皇陛下が心臓手術を受けられたのが平成24年2月18日。3月4日には退院された陛下は、3月11日には東日本大震災一周年追悼式にご出席、5月16日からはロンドンでの英女王ご即位60周年の式典に参加されるというご活躍ぶりだ。
陛下のご病気は、心臓を取り囲むように走って心筋に酸素を供給する冠動脈が流れにくくなり、胸が締め付けられるように痛む狭心症だった。手術はその冠動脈に別の血管をバイパスとして繋いで血流を良くするというもので、日本屈指の心臓外科医と言われる順天堂大学医学部の天野篤教授が担当した。
天野医師は手術後に、バイパスの血流が勢いよく流れた瞬間に「自分としても、このうえなく満足のいく結果だった」と述懐している。
退院の直前には、陛下にこう申し上げた。「手術をした血管は血流がとてもよい状態で、これから20~30年は大丈夫です。同年齢の方が日本に何人いるかわかりませんが、血流状態に関しては10指に入る心臓だと思います。」
傍らにおられた皇后陛下が、「それはようございましたね」と、嬉しそうに言われた。
天野医師が、手術の翌日、新宿方面に出かけ、帰り道、デパートの食品売り場に立ち寄ったら、知らない人から次々と声をかけられた。「天皇陛下がご健康になれば、国民も喜ぶ。みんなが元気になる」ということを身をもって実感したという。
天野医師はオフポンプ手術という手法を日本に導入したパイオニアである。従来は手術の際に心臓を一旦止め、その間は人工心肺装置を使って血液を送り込んでいた。
オフポンプ手術とは、人工心肺装置を使わずに、心臓を動かしたままで手術をする手法である。これにより、患者の負担が軽くなり術後の回復が早くなる、脳梗塞などの合併症が起こるリスクも低くなり、高齢者や持病のある人への手術も可能となる。
「心臓が動いている状態でどうやって手術するのかと不思議に思うかもしれないが、要は「集中」と「慣れ」だ。神経をグーッと研ぎ澄ませていくと動いている心臓が瞬間、止まって見える。出血していても、血が出ていないほんの一瞬がわかる。そのタイミングを見計らって、すかさず針を通す。」
「心臓外科手術に望む心境をたとえるなら、昔、決闘に向かった人々の気持ちと同じではないだろうかと感じることがある。勝負を挑み、いずれか果てるまで闘う。宮本武蔵もそう。戦国の武将もそう。」
手術での糸結び。1分間に90回、繰り返し結ぶことができるようになった。それも患者の体内の深い所での結び方、片手しか入らない時に行う結び方など、さまざまな状況での結び方がある。
しかし25年で6千人以上も手術をしても、技術を磨く道には行き止まりはない。
「むしろ、そこから先も私は、まだまだ成長していると思っている。血管のつなぎ方ひとつにも、それまでの「しっかり堅固に縫う」から、ときには「あえて緩く縫う」ことができるようになった。しなやかさを残して縫合することで、手術後の回復に良い結果が出ることもある。」
「武士道という言葉があるように、私は『医師道』というものもあると信じている」と天野医師は語る。
「医師は人の痛みを取り除く職業である。当然、世のため人のための思いがなければ医師であってはならないとさえ思う。「この人を絶対に助ける」という、熱い思いを持って、真剣勝負をしなければならない。」
医師道に限らず、どんな職業も「道」だと考え、そこで自らの技量を磨き、世のため人のために尽くしていこうと志すのが、わが国の伝統的な職業観である。この職業観は、当人に使命感とやりがいを与えるだけでなく、互いへの思いやりに満ちた世の中をつくる。医師道を行く天野医師の生き方はその模範を示している。(文責:伊勢雅臣)
天皇陛下の執刀医、天野篤の「医師道」
なんとしても患者を救うという使命感と報恩の心が「医師道」の原動力。
78歳の天皇陛下が心臓手術を受けられたのが平成24年2月18日。3月4日には退院された陛下は、3月11日には東日本大震災一周年追悼式にご出席、5月16日からはロンドンでの英女王ご即位60周年の式典に参加されるというご活躍ぶりだ。
陛下のご病気は、心臓を取り囲むように走って心筋に酸素を供給する冠動脈が流れにくくなり、胸が締め付けられるように痛む狭心症だった。手術はその冠動脈に別の血管をバイパスとして繋いで血流を良くするというもので、日本屈指の心臓外科医と言われる順天堂大学医学部の天野篤教授が担当した。
天野医師は手術後に、バイパスの血流が勢いよく流れた瞬間に「自分としても、このうえなく満足のいく結果だった」と述懐している。
退院の直前には、陛下にこう申し上げた。「手術をした血管は血流がとてもよい状態で、これから20~30年は大丈夫です。同年齢の方が日本に何人いるかわかりませんが、血流状態に関しては10指に入る心臓だと思います。」
傍らにおられた皇后陛下が、「それはようございましたね」と、嬉しそうに言われた。
天野医師が、手術の翌日、新宿方面に出かけ、帰り道、デパートの食品売り場に立ち寄ったら、知らない人から次々と声をかけられた。「天皇陛下がご健康になれば、国民も喜ぶ。みんなが元気になる」ということを身をもって実感したという。
天野医師はオフポンプ手術という手法を日本に導入したパイオニアである。従来は手術の際に心臓を一旦止め、その間は人工心肺装置を使って血液を送り込んでいた。
オフポンプ手術とは、人工心肺装置を使わずに、心臓を動かしたままで手術をする手法である。これにより、患者の負担が軽くなり術後の回復が早くなる、脳梗塞などの合併症が起こるリスクも低くなり、高齢者や持病のある人への手術も可能となる。
「心臓が動いている状態でどうやって手術するのかと不思議に思うかもしれないが、要は「集中」と「慣れ」だ。神経をグーッと研ぎ澄ませていくと動いている心臓が瞬間、止まって見える。出血していても、血が出ていないほんの一瞬がわかる。そのタイミングを見計らって、すかさず針を通す。」
「心臓外科手術に望む心境をたとえるなら、昔、決闘に向かった人々の気持ちと同じではないだろうかと感じることがある。勝負を挑み、いずれか果てるまで闘う。宮本武蔵もそう。戦国の武将もそう。」
手術での糸結び。1分間に90回、繰り返し結ぶことができるようになった。それも患者の体内の深い所での結び方、片手しか入らない時に行う結び方など、さまざまな状況での結び方がある。
しかし25年で6千人以上も手術をしても、技術を磨く道には行き止まりはない。
「むしろ、そこから先も私は、まだまだ成長していると思っている。血管のつなぎ方ひとつにも、それまでの「しっかり堅固に縫う」から、ときには「あえて緩く縫う」ことができるようになった。しなやかさを残して縫合することで、手術後の回復に良い結果が出ることもある。」
「武士道という言葉があるように、私は『医師道』というものもあると信じている」と天野医師は語る。
「医師は人の痛みを取り除く職業である。当然、世のため人のための思いがなければ医師であってはならないとさえ思う。「この人を絶対に助ける」という、熱い思いを持って、真剣勝負をしなければならない。」
医師道に限らず、どんな職業も「道」だと考え、そこで自らの技量を磨き、世のため人のために尽くしていこうと志すのが、わが国の伝統的な職業観である。この職業観は、当人に使命感とやりがいを与えるだけでなく、互いへの思いやりに満ちた世の中をつくる。医師道を行く天野医師の生き方はその模範を示している。(文責:伊勢雅臣)
2015年06月12日
韓国のMERS・街中マスク・マスク
韓国のMERS感染拡大止まらない マスク着用姿が街中にあふれ、日本メーカーに注文殺到

J-CASTニュース 6月12日(金)18時42分配信
韓国で中東呼吸症候群(MERS)の感染拡大が止まらない。2015年6月12日までで死者数は11人になり、感染者は計126人になった。
韓国機、無消毒のまま名古屋で発着 「MERS感染」の心配はないのか
マスクを着ける人が街中にあふれるとともに、外出を控える動きが広がり、韓国経済に大きな打撃を与えている。政府は対応に追われているが、メディアは政権を批判する論調を強めている。
・マスクの売り上げが前年比3600%増
もともと韓国では日本に比べてマスクをつける習慣はあまりないが、MERSの感染が広がるにつれ、外出時に着用する人が急増している。韓国メディアは連日マスク姿で街中を歩く人の写真を紙面に掲載するなど、MERSがもたらした象徴的な風景として取り上げているようだ。
聯合ニュースによると、マスクの売り上げは前年同期比で3601.5%と大幅な伸びを記録したという。
ネットには結婚式の出席者全員がマスク姿の記念写真が出回り、SNSで拡散された。後にジョーク写真と明らかになったが、大きな波紋を広げた。

こうした中で品質の高い日本製マスクが注目されている。素材メーカー「くればぁ」は韓国の商社などから注文が殺到し、15年5月20日から6月10日の期間、昨年の同じ時期に比べて売り上げは約10倍に伸びた。中河原毅専務によると、愛知県豊橋市にある同社まで、韓国から買いに来る客もいたという。
消費低迷で韓国経済に大打撃
MERSは韓国経済にも大きな打撃を与えている。感染拡大のおそれからか外出を控える人が増加し、消費が低迷している。中央日報(6月11日記事、以下いずれも日本語ウェブ版)は、「昨年のセウォル号事故直後よりも深刻」だと伝えた。
企画財政部のまとめでは6月1~7日のデパート売上は前年同期比で16.5%、大型スーパーでは3.4%減少。人が集まる施設の来場者数の落ち込みは大きく、いずれも前年同期比で映画館は54.9%、博物館は81.5%、遊園地は60.4%も下落したという。
外食も大きな影響を受けている。飲食店のカード使用額は5月の第1、2週の平均より12.3%も下がった。
韓国経済研究院の試算では、今の状況が8月末までの3か月続いた場合、国内総生産(GDP)の損失は、1年間の1.3%分に相当する20兆922億ウォン(約2兆2100億円)に上るとしている。
政府は景気低迷を懸念し、被害のあった地域や観光、宿泊業界が融資を受けられる4000億ウォン(約440億円)規模の基金をねん出。中小の医療機関には200億ウォン(約22億円)を支援し、患者には所得制限をかけずに約110万ウォン(約12万円)の緊急支援金を出す方針だ。
ただ、メディアは政府への批判を強めている。朝鮮日報は11日付社説で、初動に失敗したと朴槿恵(パク・クネ)大統領を批判。中央日報は11日付コラムでMERSの不安感が広がる原因を「恐怖の拡散は政府の力不足のためだ」と断じた。MERS感染と関係が疑われる病院の公表が遅れるなど、保健当局の情報公開が徹底できていないと批判している。また翌日の社説でも、なぜ朴大統領が記者会見を開かないのかと非難した。

J-CASTニュース 6月12日(金)18時42分配信
韓国で中東呼吸症候群(MERS)の感染拡大が止まらない。2015年6月12日までで死者数は11人になり、感染者は計126人になった。
韓国機、無消毒のまま名古屋で発着 「MERS感染」の心配はないのか
マスクを着ける人が街中にあふれるとともに、外出を控える動きが広がり、韓国経済に大きな打撃を与えている。政府は対応に追われているが、メディアは政権を批判する論調を強めている。
・マスクの売り上げが前年比3600%増
もともと韓国では日本に比べてマスクをつける習慣はあまりないが、MERSの感染が広がるにつれ、外出時に着用する人が急増している。韓国メディアは連日マスク姿で街中を歩く人の写真を紙面に掲載するなど、MERSがもたらした象徴的な風景として取り上げているようだ。
聯合ニュースによると、マスクの売り上げは前年同期比で3601.5%と大幅な伸びを記録したという。
ネットには結婚式の出席者全員がマスク姿の記念写真が出回り、SNSで拡散された。後にジョーク写真と明らかになったが、大きな波紋を広げた。

こうした中で品質の高い日本製マスクが注目されている。素材メーカー「くればぁ」は韓国の商社などから注文が殺到し、15年5月20日から6月10日の期間、昨年の同じ時期に比べて売り上げは約10倍に伸びた。中河原毅専務によると、愛知県豊橋市にある同社まで、韓国から買いに来る客もいたという。
消費低迷で韓国経済に大打撃
MERSは韓国経済にも大きな打撃を与えている。感染拡大のおそれからか外出を控える人が増加し、消費が低迷している。中央日報(6月11日記事、以下いずれも日本語ウェブ版)は、「昨年のセウォル号事故直後よりも深刻」だと伝えた。
企画財政部のまとめでは6月1~7日のデパート売上は前年同期比で16.5%、大型スーパーでは3.4%減少。人が集まる施設の来場者数の落ち込みは大きく、いずれも前年同期比で映画館は54.9%、博物館は81.5%、遊園地は60.4%も下落したという。
外食も大きな影響を受けている。飲食店のカード使用額は5月の第1、2週の平均より12.3%も下がった。
韓国経済研究院の試算では、今の状況が8月末までの3か月続いた場合、国内総生産(GDP)の損失は、1年間の1.3%分に相当する20兆922億ウォン(約2兆2100億円)に上るとしている。
政府は景気低迷を懸念し、被害のあった地域や観光、宿泊業界が融資を受けられる4000億ウォン(約440億円)規模の基金をねん出。中小の医療機関には200億ウォン(約22億円)を支援し、患者には所得制限をかけずに約110万ウォン(約12万円)の緊急支援金を出す方針だ。
ただ、メディアは政府への批判を強めている。朝鮮日報は11日付社説で、初動に失敗したと朴槿恵(パク・クネ)大統領を批判。中央日報は11日付コラムでMERSの不安感が広がる原因を「恐怖の拡散は政府の力不足のためだ」と断じた。MERS感染と関係が疑われる病院の公表が遅れるなど、保健当局の情報公開が徹底できていないと批判している。また翌日の社説でも、なぜ朴大統領が記者会見を開かないのかと非難した。
2015年05月27日
アンジーの乳房切除・卵巣摘出の件
アンジーが行った乳房切除・卵巣摘出について考える
アー・ユー・ハッピーサイトより 201506
http://www.are-you-happy.com/article_opinion/4469
今年3月24日、女優のアンジーことアンジェリーナ・ジョリーさん(39歳)が、卵巣がんの予防のため、卵巣と卵管の摘出手術を行ったことを「ニューヨーク・タイムズ」誌で告白。そのニュースは瞬く間に世界を駆け巡った。
アンジーは2013年に遺伝子検査を受け、医師から、「乳がんになるリスクが87%、卵巣がんになるリスクが50%ある」という宣告を受け、同年、乳がん予防のため、両乳房の切除手術と同時再建手術を済ませていた。
乳がんになるリスクは5%以下になったというが、その後受けた血液検査で卵巣がんの可能性を指摘され、さらに卵巣と卵管の切除手術を決意したのだ。
この決断は「簡単ではなかった」とアンジーは語っているが、手術に踏み切った背景には理由があった。2007年、最愛の母を、2013年には叔母を、いずれも長期のがん闘病の末に亡くしていたのだ。
アンジーは、俳優ブラッド・ピット(51歳)との間にもうけた3人の実子のほかに、養子3人の計6人の子供を育てている。「ニューヨーク・タイムズ」誌に寄稿した手記の中で、「子供たちが『ママを卵巣がんで亡くした』と決して言わないで済むように」と語ったように、“母親としての思い”が手術に踏み切らせたのだった。

産婦人科専門医の阿部結貴さんは、アンジーの決断についてこう話す。
「アメリカのガイドラインによると、HBOCの方の乳がん検診は、25歳から半年毎の乳房触診、毎年のマンモグラフィーとMRIを受けることになっており、乳房の切除手術の選択肢について相談する、となっています。
卵巣がんは早期発見が難しいのですが、手術をしない場合は35歳から半年毎の経膣超音波検査+腫瘍マーカー採血という検診方法が勧められます。卵巣・卵管摘出手術は、がんのリスクや手術の利点欠点などをよく話し合ったうえで、35~40歳または出産終了時に勧めることになっています。両方の卵巣がなくなると、通常、妊娠・出産はできなくなります。また女性ホルモンが出なくなるため更年期症状が出現し、早くに閉経するため、ホルモン補充療法が必要になります。
がんが起こる原因としては大きく環境要因(生活習慣)と、遺伝要因があるといわれており、遺伝だけで必ずがんになるわけではありません。治療法の選択には、がんに対する考え方が大きく影響してくるのではないでしょうか」
日本では、大学病院をはじめとする全国65件以上の病院で、遺伝子検査が行われている。保険が適用されないため、全額自己負担で30万円前後と高額だ。しかし今後、遺伝子検査や、がん予防のための摘出手術がメジャーになる可能性もある。
大川総裁は、著書『未来の法』で、「ガンは、各人が、心の悩みによって、つくることができるものです(過労や強度の責任感が原因の場合もある)。自分でつくることができるものであるならば、自分で消すこともまた可能です。自分で治すことも可能なのです」と説いている。
遺伝子が原因でがんの発症リスクが高まることも否めないが、心のあり方ががんを作り出しているという真実を知り、自らの心と向き合っていかなくては、本当の意味で、リスクを取り去ることはできない。それを怠れば、発症する場所を変えて病変は現れてくるだろう。ガンは、その部分を取り除けば終わり、ではないのだ。
心の持ち方が関係して病気ができるというメカニズムを知ったうえで、生きていくために大切な肉体をどうコントロールしていくかが、大切なのかもしれない。
がん予防のため、卵巣摘出を選択したアンジー。この決断は、吉と出るか?
アー・ユー・ハッピーサイトより 201506
http://www.are-you-happy.com/article_opinion/4469
今年3月24日、女優のアンジーことアンジェリーナ・ジョリーさん(39歳)が、卵巣がんの予防のため、卵巣と卵管の摘出手術を行ったことを「ニューヨーク・タイムズ」誌で告白。そのニュースは瞬く間に世界を駆け巡った。
アンジーは2013年に遺伝子検査を受け、医師から、「乳がんになるリスクが87%、卵巣がんになるリスクが50%ある」という宣告を受け、同年、乳がん予防のため、両乳房の切除手術と同時再建手術を済ませていた。
乳がんになるリスクは5%以下になったというが、その後受けた血液検査で卵巣がんの可能性を指摘され、さらに卵巣と卵管の切除手術を決意したのだ。
この決断は「簡単ではなかった」とアンジーは語っているが、手術に踏み切った背景には理由があった。2007年、最愛の母を、2013年には叔母を、いずれも長期のがん闘病の末に亡くしていたのだ。
アンジーは、俳優ブラッド・ピット(51歳)との間にもうけた3人の実子のほかに、養子3人の計6人の子供を育てている。「ニューヨーク・タイムズ」誌に寄稿した手記の中で、「子供たちが『ママを卵巣がんで亡くした』と決して言わないで済むように」と語ったように、“母親としての思い”が手術に踏み切らせたのだった。

産婦人科専門医の阿部結貴さんは、アンジーの決断についてこう話す。
「アメリカのガイドラインによると、HBOCの方の乳がん検診は、25歳から半年毎の乳房触診、毎年のマンモグラフィーとMRIを受けることになっており、乳房の切除手術の選択肢について相談する、となっています。
卵巣がんは早期発見が難しいのですが、手術をしない場合は35歳から半年毎の経膣超音波検査+腫瘍マーカー採血という検診方法が勧められます。卵巣・卵管摘出手術は、がんのリスクや手術の利点欠点などをよく話し合ったうえで、35~40歳または出産終了時に勧めることになっています。両方の卵巣がなくなると、通常、妊娠・出産はできなくなります。また女性ホルモンが出なくなるため更年期症状が出現し、早くに閉経するため、ホルモン補充療法が必要になります。
がんが起こる原因としては大きく環境要因(生活習慣)と、遺伝要因があるといわれており、遺伝だけで必ずがんになるわけではありません。治療法の選択には、がんに対する考え方が大きく影響してくるのではないでしょうか」
日本では、大学病院をはじめとする全国65件以上の病院で、遺伝子検査が行われている。保険が適用されないため、全額自己負担で30万円前後と高額だ。しかし今後、遺伝子検査や、がん予防のための摘出手術がメジャーになる可能性もある。
大川総裁は、著書『未来の法』で、「ガンは、各人が、心の悩みによって、つくることができるものです(過労や強度の責任感が原因の場合もある)。自分でつくることができるものであるならば、自分で消すこともまた可能です。自分で治すことも可能なのです」と説いている。
遺伝子が原因でがんの発症リスクが高まることも否めないが、心のあり方ががんを作り出しているという真実を知り、自らの心と向き合っていかなくては、本当の意味で、リスクを取り去ることはできない。それを怠れば、発症する場所を変えて病変は現れてくるだろう。ガンは、その部分を取り除けば終わり、ではないのだ。
心の持ち方が関係して病気ができるというメカニズムを知ったうえで、生きていくために大切な肉体をどうコントロールしていくかが、大切なのかもしれない。
がん予防のため、卵巣摘出を選択したアンジー。この決断は、吉と出るか?
2015年05月17日
大山のぶ代さん認知症・魂は健全
「ドラえもん」の大山のぶ代さんが認知症 病には人生の課題が隠されている
ザ・リバティ・ウェブより、抜粋・編集 2015.05.15
俳優の砂川啓介さんは、15日、アニメ「ドラえもん」の声優で知られる妻、大山のぶ代さんが認知症を患っているとラジオで公表したことについて、「言いたくなかったが、隠しているのが、つらくなってきた」と苦しい胸の内を明かした。
砂川さんによると、大山さんは2分前のことを覚えておらず、入浴も一人ではできない状態。仕事は何とか台本を見ながら行っているものの、得意な料理も含めて家事はほとんどできず、「私もうダメだ」とため息を漏らし、自信を喪失しているという。
大山さん本人はもちろん、長年連れ添い、人生の苦楽を共にした妻が病と闘っている砂川さんの苦しみも計り知れない。
認知症の患者数は年々増加しており、85歳以上の約4人に1人だと言われている。認知症はもはや他人事とは言えないが、認知症の人にはどうやって接していけば良いのだろうか。
認知症の人の魂は健全
大川総裁は著書『心と体のほんとうの関係』(主な症例・健康の秘訣、疲労の予防法、ガンの予防、臓器移植、ウツの原因と対策、ダイエット、金縛り、性同一性障害、中絶、エイズ、インフルエンザ、アトピー性皮膚炎、自閉症、子供の障害、どもり、リウマチ、失明、看護・介護の心がけ、心臓病予防・・・)の中で、認知症についてこう述べている。
「認知症になったからといって、天上界に行けないということはありません」「肉体を動かす、機械、としての脳が傷み、正常に働かなくなったとしても、魂のほうは別に何ともないのですね。正常であり、元のままなのです」
人間の本質は肉体ではなく霊であるという霊的真実を知れば、認知症が「全てを失う病気」ではないことが分かる。脳が損傷を受けて認知症を発症しても、魂は健全なのだ。
老化による肉体的苦しみは誰もが何かしら経験するものだ。それは単なる苦しみではなく、人生の課題につながるものであったり、肉体を脱ぎ捨ててあの世へ還るための準備の意味がある。また、生前、神仏の心に叶う生き方をしていたならば、病などで苦しんだ分、あの世へ還ったときの幸福感は大きくなる。
また、家族にとって、認知症患者の介護は愛の実践行でもある。かつてお世話になった家族に無私な思いで恩返しすることは、介護する側にとって魂の大きな成長の機会となり、功徳を積むことになる。治療という意味では、家族にできることは少ないかもしれない。しかし、愛ある言葉で、認知症患者の不安や孤独感を和らげ、魂の癒しを与えることは、目に見える形で現れなくても、大きな意味があると言える。(冨)
ザ・リバティ・ウェブより、抜粋・編集 2015.05.15
俳優の砂川啓介さんは、15日、アニメ「ドラえもん」の声優で知られる妻、大山のぶ代さんが認知症を患っているとラジオで公表したことについて、「言いたくなかったが、隠しているのが、つらくなってきた」と苦しい胸の内を明かした。
砂川さんによると、大山さんは2分前のことを覚えておらず、入浴も一人ではできない状態。仕事は何とか台本を見ながら行っているものの、得意な料理も含めて家事はほとんどできず、「私もうダメだ」とため息を漏らし、自信を喪失しているという。
大山さん本人はもちろん、長年連れ添い、人生の苦楽を共にした妻が病と闘っている砂川さんの苦しみも計り知れない。
認知症の患者数は年々増加しており、85歳以上の約4人に1人だと言われている。認知症はもはや他人事とは言えないが、認知症の人にはどうやって接していけば良いのだろうか。
認知症の人の魂は健全
大川総裁は著書『心と体のほんとうの関係』(主な症例・健康の秘訣、疲労の予防法、ガンの予防、臓器移植、ウツの原因と対策、ダイエット、金縛り、性同一性障害、中絶、エイズ、インフルエンザ、アトピー性皮膚炎、自閉症、子供の障害、どもり、リウマチ、失明、看護・介護の心がけ、心臓病予防・・・)の中で、認知症についてこう述べている。
「認知症になったからといって、天上界に行けないということはありません」「肉体を動かす、機械、としての脳が傷み、正常に働かなくなったとしても、魂のほうは別に何ともないのですね。正常であり、元のままなのです」
人間の本質は肉体ではなく霊であるという霊的真実を知れば、認知症が「全てを失う病気」ではないことが分かる。脳が損傷を受けて認知症を発症しても、魂は健全なのだ。
老化による肉体的苦しみは誰もが何かしら経験するものだ。それは単なる苦しみではなく、人生の課題につながるものであったり、肉体を脱ぎ捨ててあの世へ還るための準備の意味がある。また、生前、神仏の心に叶う生き方をしていたならば、病などで苦しんだ分、あの世へ還ったときの幸福感は大きくなる。
また、家族にとって、認知症患者の介護は愛の実践行でもある。かつてお世話になった家族に無私な思いで恩返しすることは、介護する側にとって魂の大きな成長の機会となり、功徳を積むことになる。治療という意味では、家族にできることは少ないかもしれない。しかし、愛ある言葉で、認知症患者の不安や孤独感を和らげ、魂の癒しを与えることは、目に見える形で現れなくても、大きな意味があると言える。(冨)
2015年05月15日
悩み相談・アスペルガー症候群
アスペルガー症候群は天才の代名詞みたいなものなのかも知れませんね~。
正しく向き合うことで、天才的な能力を引き出せるのではないでしょうか、アインシュタイン、ミケランジェロ、グレン・グールドのように・・
ハッピー・サイエンス・サイトより、抜粋・編集2015.05.14
http://info.happy-science.jp/2015/13370/
アスペルガー症候群のお子さまについて

支援学級に通う小学校4年生の次男が、学校で友達や先生に何か言われると、すぐにかっとなってしまい、学校から抜け出したり、家に帰ってきてしまいます。また、言われたことで「みんなが僕をいじめるから学校に行きたくない」と言っています。どうしたらいいでしょうか。
【ハピママしあわせ相談室 Vol.3】
子どもは傷ついた自尊心を何とかしてほしい
途中で学校を抜け出して帰ってくるのは、確かに危険があるし、大変なことだと思います。ですが、「こういう理由があるから学校を途中で抜けてきちゃだめなんだよ」「お友達は別に君のことをいじめてるんじゃなくて、仲良くしたいからそうしてくるんだよ」という説明でそれをやめさせようとしても、本人は納得しないと思います。
まわりから見れば、それはたいしたトラブルでもないし、言葉を発した相手の真意をわからせれば解決すると思って、「みんなは、そんなつもりで言ってないよ」などと言いたくなるものですが、お子さんは、別に友達や先生との関係を仲裁してほしいわけではありません。
ですから、表面的に出ている行動をなんとか収めようとか、友達や先生との間を取り持つ方向のアドバイスをしても、効果はありません。そういう時に本当にしてあげなくてはいけないのは、自信を取り戻させてあげることです。
子どもの精神的なすばらしさをほめてあげる
そのために、お母さんは、お子さんの得意なところや、お子さんが好きでいつもしていることを見つけて、ほめてあげてください。続けていると、少しずつ、そういう行動が減っていくのではないかと思います。
ほめるポイントは、「やさしい」「ルールを守れる」「正義感が強い」といった精神的な意味でのすばらしさ。アスペルガーという診断が出るお子さんには、割と正義感が強いタイプのお子さんが多く、ちょっとしたことが許せなかったりして、トラブルのもとにもなるのですが、本人は決してトラブルを起こそうと思ってやっているわけではありません。
ものすごく強い正義感があって、それにはまらないことが起きた時に許せなくて言ってしまうだけです。もともとの動機はそういうところにある子が多いので、その心根のすばらしさをほめてあげるといいですね。
傷つきかけた自尊心を元通りにする言葉が効果的
あとは、お家でお手伝いをしてもらった時に、「すごく助かったよ」「○○ちゃんがこういうことをやってくれて、お母さんうれしい」「お母さんが困っていると思ってやってくれたの?ありがとう」とほめるなど、傷つきかけている、崩れかけている自尊心を、少しずつ元の形に戻していってあげられるような言葉をかけることが、効果的です。
起きている行動だけを何とかしようと思って、表面的な解決だけをしても、傷ついた自尊心が元通りにならない限り、また、いろいろなところでトラブルが出てくる可能性があります。お子さんがいちばんうれしいのは、お母さんにほめてもらうことなので、ほめるポイントをしっかりと見つけて、ほめていってあげてほしいと思います。
正しく向き合うことで、天才的な能力を引き出せるのではないでしょうか、アインシュタイン、ミケランジェロ、グレン・グールドのように・・
ハッピー・サイエンス・サイトより、抜粋・編集2015.05.14
http://info.happy-science.jp/2015/13370/
アスペルガー症候群のお子さまについて

支援学級に通う小学校4年生の次男が、学校で友達や先生に何か言われると、すぐにかっとなってしまい、学校から抜け出したり、家に帰ってきてしまいます。また、言われたことで「みんなが僕をいじめるから学校に行きたくない」と言っています。どうしたらいいでしょうか。
【ハピママしあわせ相談室 Vol.3】
子どもは傷ついた自尊心を何とかしてほしい
途中で学校を抜け出して帰ってくるのは、確かに危険があるし、大変なことだと思います。ですが、「こういう理由があるから学校を途中で抜けてきちゃだめなんだよ」「お友達は別に君のことをいじめてるんじゃなくて、仲良くしたいからそうしてくるんだよ」という説明でそれをやめさせようとしても、本人は納得しないと思います。
まわりから見れば、それはたいしたトラブルでもないし、言葉を発した相手の真意をわからせれば解決すると思って、「みんなは、そんなつもりで言ってないよ」などと言いたくなるものですが、お子さんは、別に友達や先生との関係を仲裁してほしいわけではありません。
ですから、表面的に出ている行動をなんとか収めようとか、友達や先生との間を取り持つ方向のアドバイスをしても、効果はありません。そういう時に本当にしてあげなくてはいけないのは、自信を取り戻させてあげることです。
子どもの精神的なすばらしさをほめてあげる
そのために、お母さんは、お子さんの得意なところや、お子さんが好きでいつもしていることを見つけて、ほめてあげてください。続けていると、少しずつ、そういう行動が減っていくのではないかと思います。
ほめるポイントは、「やさしい」「ルールを守れる」「正義感が強い」といった精神的な意味でのすばらしさ。アスペルガーという診断が出るお子さんには、割と正義感が強いタイプのお子さんが多く、ちょっとしたことが許せなかったりして、トラブルのもとにもなるのですが、本人は決してトラブルを起こそうと思ってやっているわけではありません。
ものすごく強い正義感があって、それにはまらないことが起きた時に許せなくて言ってしまうだけです。もともとの動機はそういうところにある子が多いので、その心根のすばらしさをほめてあげるといいですね。
傷つきかけた自尊心を元通りにする言葉が効果的
あとは、お家でお手伝いをしてもらった時に、「すごく助かったよ」「○○ちゃんがこういうことをやってくれて、お母さんうれしい」「お母さんが困っていると思ってやってくれたの?ありがとう」とほめるなど、傷つきかけている、崩れかけている自尊心を、少しずつ元の形に戻していってあげられるような言葉をかけることが、効果的です。
起きている行動だけを何とかしようと思って、表面的な解決だけをしても、傷ついた自尊心が元通りにならない限り、また、いろいろなところでトラブルが出てくる可能性があります。お子さんがいちばんうれしいのは、お母さんにほめてもらうことなので、ほめるポイントをしっかりと見つけて、ほめていってあげてほしいと思います。
2015年04月27日
アトピーが治った!
ボイシーサイトより、抜粋・編集2013.10.16
Mさん(40代・男性)
私は、幼いころからアレルギー体質でした。アトピー性皮膚炎や鼻炎、ぜん息など、症状を変えながらアレルギー反応を繰り返す、いわゆる「アレルギー・マーチ(アレルギーの行進)」だったのです。
幸福の科学では、病気の原因の7割は「心」にあると説かれています。医学的にも、アトピーの原因の一つは精神的なストレスとされます。
生活習慣の改善や薬でよくなっても、しばらくすると再発するのは、根本にある心に問題があるからに違いありません。
幸福の科学に入会したものの、本格的に心の修行をしてこなかった、そのツケが回ってきたのだと思いました。今度こそ自己変革して、アトピーを克服しようと心に決めました。
そう決意した直後、雑誌「ザ・リバティ」に、アトピーに関する皮膚科医の方の記事を見つけました。
「皮膚は自分と外界、とりわけ他人との境界線です。このことからも、他人に対する拒絶感が、アトピー性皮膚炎を起こし、また悪化させているように思えます」(「ザ・リバティ」1997年12月号より)
「他人への拒絶感」という言葉が、印象に残りました。
アトピーを根本から解決するため、とにかく対人関係をよくしようと思った私は、まず、明るい印象を与えるために、笑顔や明るい声のトーンを心がけました。同時に、「思い」にも気をつけました。
「自分が、自分が」という気持ちを抑え、まず、お客様の話を丁寧に伺い、理解するように心がけたのです。
「それにしても、どうして人づき合いが苦手になったんだろう」
私はさらに深く、自分自身の心を見つめていきました。
私は学生時代から、どこか斜に構えたところのある卑屈な性格でした。人の好意やほめ言葉は素直に受け取らず、批判には過剰反応してカーッと怒る。そうした傾向性があったのです。
どうして、そのような性格になったのか、自分の人生をふり返っていくと、子供の頃の記憶がよみがえってきました。
私の両親は子供への期待が大きく、私に小学校、中学校、高校と、偏差値の高い学校を受験をさせました。しかし、ことごとく失敗――。
その時に心に刻まれた劣等感を、私はずっと引きずり、これ以上、傷つけられたくないと、他人に心を閉ざしていたのです。これこそ、問題の「根っこ」でした。
これまでの人生を前後際断(ぜんごさいだん)し、まったく新しい自分に生まれ変わろうと決意した私は、35歳の時、総本山・正心館(しょうしんかん)で「起死回生の秘法」を受けました。
導師が経文(きょうもん)を読み上げると、仏の慈悲が胸にしみ入ってきました。そして、自分もまた、仏の子として光り輝く存在であることに、気づくことができたのです。
劣等感から解き放たれ、100%の安心感を得た瞬間でした。
もう人の目を気にしたり、人と比べたりするのはやめよう。自分自身の成長を大事にしようと、私は心から誓ったのです。
そのような心の変革をしてから今日まで、以前のようなアトピーは一度も発症していません。
アトピーの克服を通して、「心には病を治す力がある」ということを、身をもって体験することができました。
この記事は、隔月発刊の「ザ・伝道」第152号より転載し、編集を加えたものです。

Mさん(40代・男性)
私は、幼いころからアレルギー体質でした。アトピー性皮膚炎や鼻炎、ぜん息など、症状を変えながらアレルギー反応を繰り返す、いわゆる「アレルギー・マーチ(アレルギーの行進)」だったのです。
幸福の科学では、病気の原因の7割は「心」にあると説かれています。医学的にも、アトピーの原因の一つは精神的なストレスとされます。
生活習慣の改善や薬でよくなっても、しばらくすると再発するのは、根本にある心に問題があるからに違いありません。
幸福の科学に入会したものの、本格的に心の修行をしてこなかった、そのツケが回ってきたのだと思いました。今度こそ自己変革して、アトピーを克服しようと心に決めました。
そう決意した直後、雑誌「ザ・リバティ」に、アトピーに関する皮膚科医の方の記事を見つけました。
「皮膚は自分と外界、とりわけ他人との境界線です。このことからも、他人に対する拒絶感が、アトピー性皮膚炎を起こし、また悪化させているように思えます」(「ザ・リバティ」1997年12月号より)
「他人への拒絶感」という言葉が、印象に残りました。
アトピーを根本から解決するため、とにかく対人関係をよくしようと思った私は、まず、明るい印象を与えるために、笑顔や明るい声のトーンを心がけました。同時に、「思い」にも気をつけました。
「自分が、自分が」という気持ちを抑え、まず、お客様の話を丁寧に伺い、理解するように心がけたのです。
「それにしても、どうして人づき合いが苦手になったんだろう」
私はさらに深く、自分自身の心を見つめていきました。
私は学生時代から、どこか斜に構えたところのある卑屈な性格でした。人の好意やほめ言葉は素直に受け取らず、批判には過剰反応してカーッと怒る。そうした傾向性があったのです。
どうして、そのような性格になったのか、自分の人生をふり返っていくと、子供の頃の記憶がよみがえってきました。
私の両親は子供への期待が大きく、私に小学校、中学校、高校と、偏差値の高い学校を受験をさせました。しかし、ことごとく失敗――。
その時に心に刻まれた劣等感を、私はずっと引きずり、これ以上、傷つけられたくないと、他人に心を閉ざしていたのです。これこそ、問題の「根っこ」でした。
これまでの人生を前後際断(ぜんごさいだん)し、まったく新しい自分に生まれ変わろうと決意した私は、35歳の時、総本山・正心館(しょうしんかん)で「起死回生の秘法」を受けました。
導師が経文(きょうもん)を読み上げると、仏の慈悲が胸にしみ入ってきました。そして、自分もまた、仏の子として光り輝く存在であることに、気づくことができたのです。
劣等感から解き放たれ、100%の安心感を得た瞬間でした。
もう人の目を気にしたり、人と比べたりするのはやめよう。自分自身の成長を大事にしようと、私は心から誓ったのです。
そのような心の変革をしてから今日まで、以前のようなアトピーは一度も発症していません。
アトピーの克服を通して、「心には病を治す力がある」ということを、身をもって体験することができました。
この記事は、隔月発刊の「ザ・伝道」第152号より転載し、編集を加えたものです。

2015年04月24日
三大・間違った子供の叱り方

子育て110番 【実践・正しい叱り方講座2】ここが親の正念場。 叱るときは、真剣に!
アー・ユー・ハッピーサイトより、抜粋・編集
子供の叱り方、そのままでいい?
前回の叱り方講座1で、「ガミガミ叱ってばかりもよくないし、まったく叱らないのもよくない」というお話をしました。
ガミガミママも、まったく叱らないママも、「正しい叱り方を知らない」という点では一緒です。子供の心にきちんと届く叱り方、子供が自立し成長していく方向へと導く叱り方を知っていれば、親は、毎日ガミガミ叱る必要がなくなるはずです。「言っても言っても子供が同じことをくり返す」のは、子供の性格の問題ではなく、親の叱り方の問題でしょう。
また、まったく叱らない親は、「叱るのは悪」という強固な信念を持っているのかというと、そうでもありません。「どう叱っていいかわからない」「叱ったら子供の性格が歪むんじゃないかと不安」「ともかく頑固なわが子にお手上げ」などなど、ネガティブな感情で叱らないことを選択しているように見受けられます。
どちらのママも、内心では「子育てが苦しい、難しい」「本当は、これでいいはずがない」と、きっと感じていることでしょう。それなら、今日から間違った叱り方を止めて、正しい叱り方を実践する努力をすればいいのです。
三大・間違った叱り方
よく見かける〝三大・間違った叱り方〟は「にらむ・怒鳴る・叩く」です。
動物は、相手を負かしたり言うことをきかせたりするために「威嚇」という方法をとります。歯をむいたり、吼えたり、攻撃をしたりして恐がらせ、「私のほうが強いんだぞ。逆らったら恐い目に合うぞ」と脅すわけです。
ママの中には、動物的本能でこれをやってしまう人がいますが、もし自分が同じことを他の人にされたらどう感じるかを考えてほしいのです。きっと心が傷つくはずです。叱ることは必要ですが、愛のない方法や心を傷つける方法で叱ってはいけません。
温かいまなざしと、真剣み
子供には、日ごろは温かいまなざしとやさしい愛を注ぎ、悪いことをしたら、真剣に叱りましょう。恐い顔はいりません。子供を恐がらせるのではなく、「いけないことだ」と悟らせるのです。幼くとも侮らず、人間として誠実に向き合い、真剣なまなざしと真剣な言葉で愛を込めて導きましょう。
特に3歳半未満の子供には、言葉や理屈はまだ十分に届きません。その分、大人の真剣みこそが伝わります。
お教室で、3歳になったばかりの女の子がよその子のおもちゃを取って泣かせてしまい、ママは「どうせ言ってもきかない」とあきらめ顔でしたが、私はその子を抱きしめ、お顔とお顔10センチの距離で、穏やかに真剣にお話ししました。「お友達のおもちゃを取ってはいけないよ」「やだ」「いやでも、取ってはいけません」「やだ」「おくだせんせいは、一歩も引かないよ。一時間でも二時間でもこうしてキミにお話しできる。おもちゃはお友達に返しましょう。キミならわかる」―― やがて女の子は、自分から歩いていっておもちゃを返し、誇らしげな笑顔で私を見て、また楽しく遊び始めました。
大切なわが子です。どうか恐れず、信じて、真剣に導いてあげましょう。
奥田敬子 Keiko Okuda
早稲田大学第一文学部哲学科卒業。一男一女の母。 現在、幼児教室エンゼルプランVで1~6歳の幼児200人を指導。毎クラス15分間の親向け「天使をはぐくむ子育て教室」が好評。
2015年03月13日
新生児取り違え・子育てはこう考えるよ
これも何かの縁、とはよく言ったものですね。
実際、良しにつけ悪しきにつけ、印象に残るような人との関わり合いは、実は縁があり、過去からず~~っと続いている場合が多いようですね。
ですから、新生児の取り違えでの、親子関係も、過去世から縁深き人だった可能性が高いと思いますね。
この縁を大切にしたいものですね~。
新生児取り違えも「これまで通り暮らしていく」 魂の視点で親子の絆を考える
2015.03.11 ザ・リバティ・ウェブより、抜粋・編集
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9318
親子の絆とは、遺伝子の繋がりか、はたまた育てられたという事実か……と考えさせられるニュースが相次いで報じられた。
フランス・カンヌの病院で20年以上前に新生児を取り違えられた事件を巡り、2家族が病院を相手取り起こしていた訴訟で、裁判所は病院側に200万ユーロ(日本円で約2億8千万円)近い賠償の支払いを命じた(2月10日付AFP)。
この事件の原告のマノン・セラーノさんは10歳の時、母・ソフィーさんと血の繋がりがないことがわかった。その後、マノンさんの実の両親と、ソフィーさんの実の娘とは再会したが、話し合いの結果、それぞれの子供を元の親に戻すことなく、それまで通り家族として暮らしていくことを決めたという(ニューヨークタイムズ紙)。
新生児取り違えは、日本でも創作やノンフィクション作品の題材ともなっている。2013年に公開され、大ヒットした映画「そして父になる」は、取り違えた子供を血の繋がった親が引き取るというストーリーだった。この映画のように、日本では育ての親より生みの親を優先することも少なくない。
また、イギリスでは今年、「ヒトの受精と胎生学法」の改正法が可決・成立した。これにより、異常なミトコンドリアを持つ卵子から正常な卵子へ核を移植し出産することでミトコンドリア病の発症を防ぐことができるようになる。遺伝子情報は核だけでなく移植先のミトコンドリアなどにも含まれるため、2人の母親と父親の「3人の親」の遺伝情報を受け継いだ新生児が誕生することになる。このように、生殖医療が進めば進むほど、「親子」をどう考えるかは混乱するだろう。
今、焦点になっているのは「育ての親」か「生みの親」か、あるいは、血の繋がりがあるかないかだ。しかし、人間の本質は、肉体ではなく、その中に宿る魂である。こうした視点から考えると、血の繋がりのみを重視することには問題がある。
人間は、生まれる前にあの世で人生計画を立ててきており、親となる魂とも約束している。取り違えも本人が修行のために選択して生まれてきた可能性もあるのだ。
たとえ血が繋がっていなかったとしても、育ての親となった相手は何度も生まれ変わる中で魂の絆を深めた相手であるかもしれない。霊的視点を持つことで、親子のとらえ方や選択肢も変わるのではないか。 (悠)
実際、良しにつけ悪しきにつけ、印象に残るような人との関わり合いは、実は縁があり、過去からず~~っと続いている場合が多いようですね。
ですから、新生児の取り違えでの、親子関係も、過去世から縁深き人だった可能性が高いと思いますね。
この縁を大切にしたいものですね~。
新生児取り違えも「これまで通り暮らしていく」 魂の視点で親子の絆を考える
2015.03.11 ザ・リバティ・ウェブより、抜粋・編集
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9318
親子の絆とは、遺伝子の繋がりか、はたまた育てられたという事実か……と考えさせられるニュースが相次いで報じられた。
フランス・カンヌの病院で20年以上前に新生児を取り違えられた事件を巡り、2家族が病院を相手取り起こしていた訴訟で、裁判所は病院側に200万ユーロ(日本円で約2億8千万円)近い賠償の支払いを命じた(2月10日付AFP)。
この事件の原告のマノン・セラーノさんは10歳の時、母・ソフィーさんと血の繋がりがないことがわかった。その後、マノンさんの実の両親と、ソフィーさんの実の娘とは再会したが、話し合いの結果、それぞれの子供を元の親に戻すことなく、それまで通り家族として暮らしていくことを決めたという(ニューヨークタイムズ紙)。
新生児取り違えは、日本でも創作やノンフィクション作品の題材ともなっている。2013年に公開され、大ヒットした映画「そして父になる」は、取り違えた子供を血の繋がった親が引き取るというストーリーだった。この映画のように、日本では育ての親より生みの親を優先することも少なくない。
また、イギリスでは今年、「ヒトの受精と胎生学法」の改正法が可決・成立した。これにより、異常なミトコンドリアを持つ卵子から正常な卵子へ核を移植し出産することでミトコンドリア病の発症を防ぐことができるようになる。遺伝子情報は核だけでなく移植先のミトコンドリアなどにも含まれるため、2人の母親と父親の「3人の親」の遺伝情報を受け継いだ新生児が誕生することになる。このように、生殖医療が進めば進むほど、「親子」をどう考えるかは混乱するだろう。
今、焦点になっているのは「育ての親」か「生みの親」か、あるいは、血の繋がりがあるかないかだ。しかし、人間の本質は、肉体ではなく、その中に宿る魂である。こうした視点から考えると、血の繋がりのみを重視することには問題がある。
人間は、生まれる前にあの世で人生計画を立ててきており、親となる魂とも約束している。取り違えも本人が修行のために選択して生まれてきた可能性もあるのだ。
たとえ血が繋がっていなかったとしても、育ての親となった相手は何度も生まれ変わる中で魂の絆を深めた相手であるかもしれない。霊的視点を持つことで、親子のとらえ方や選択肢も変わるのではないか。 (悠)